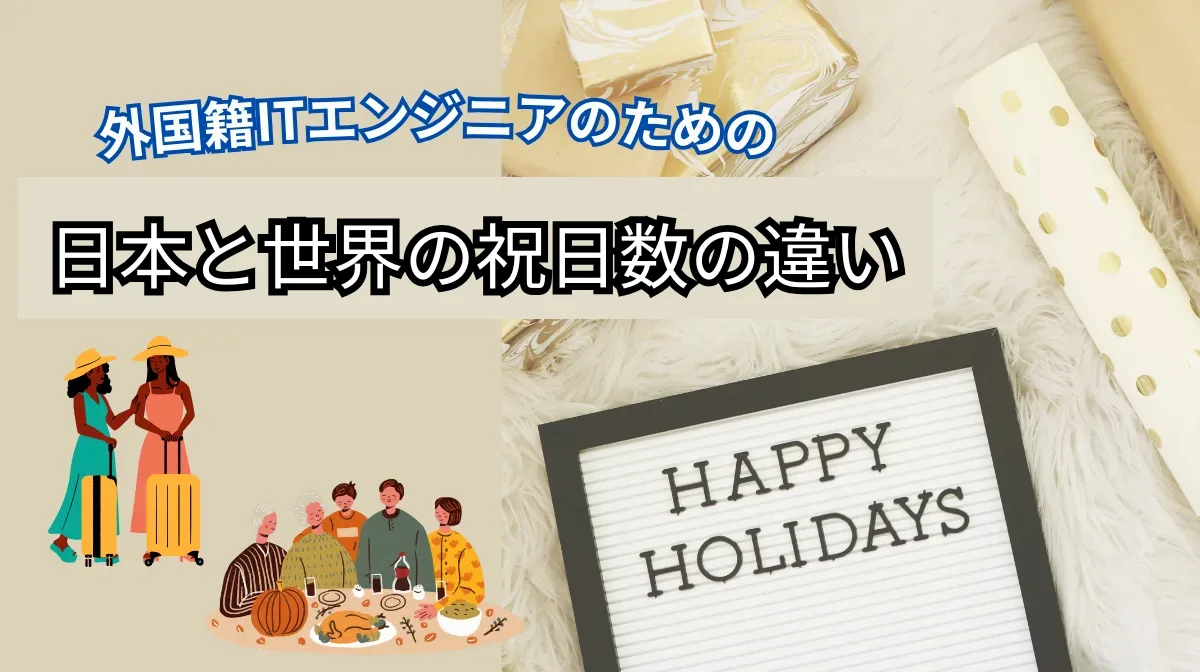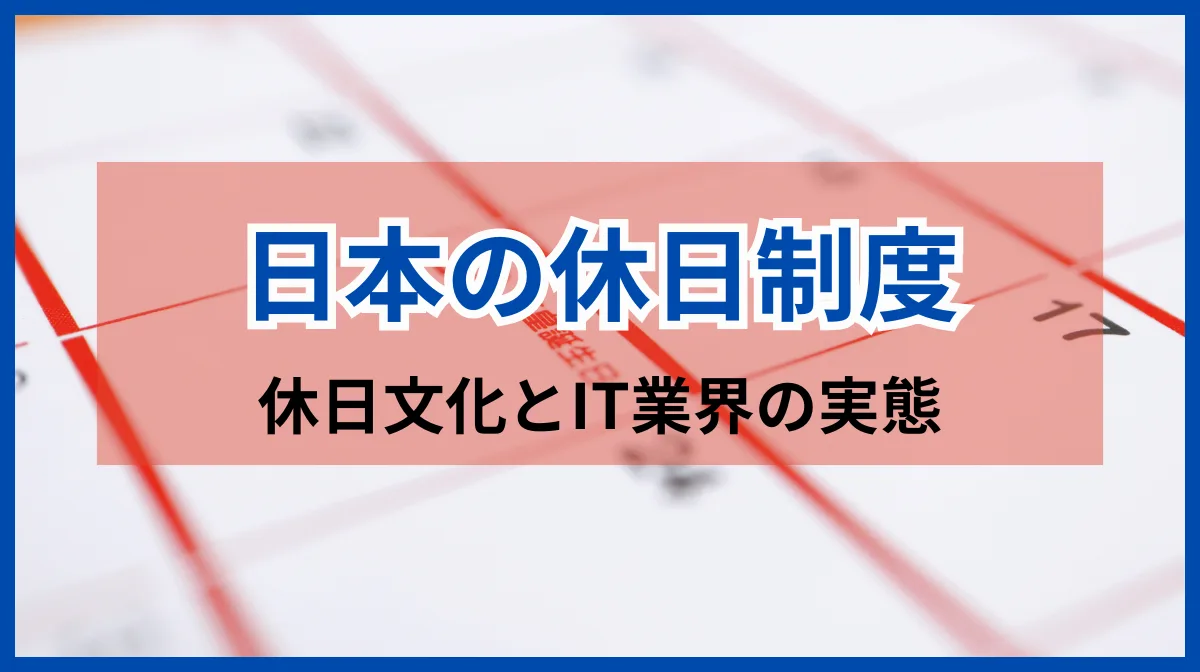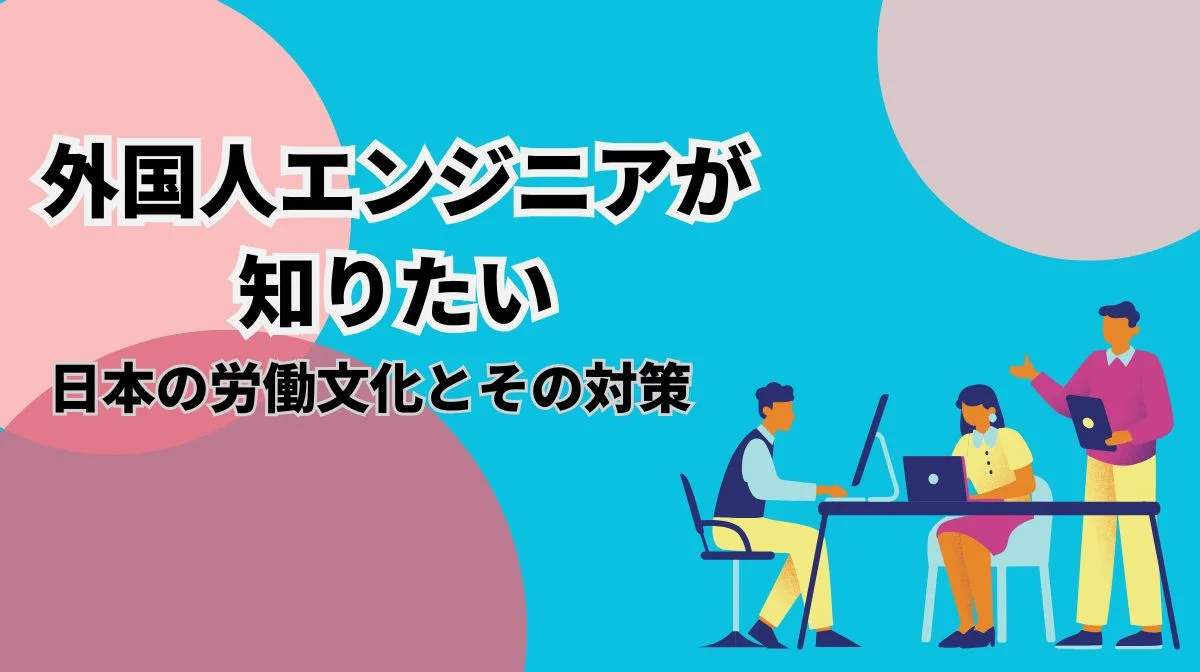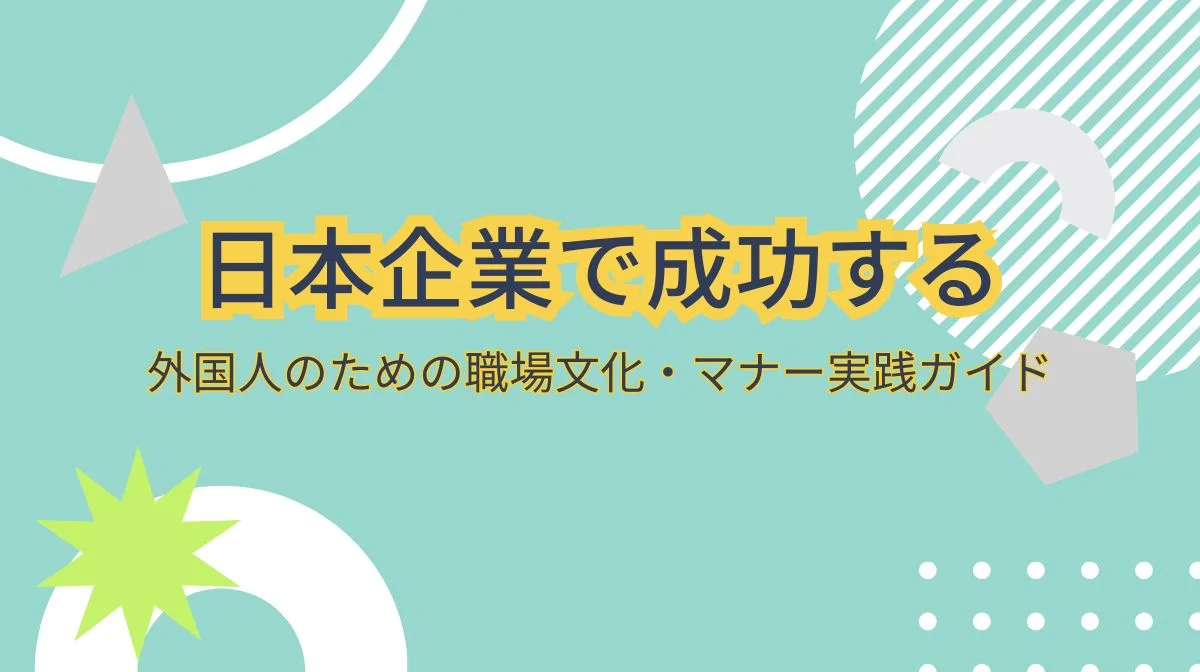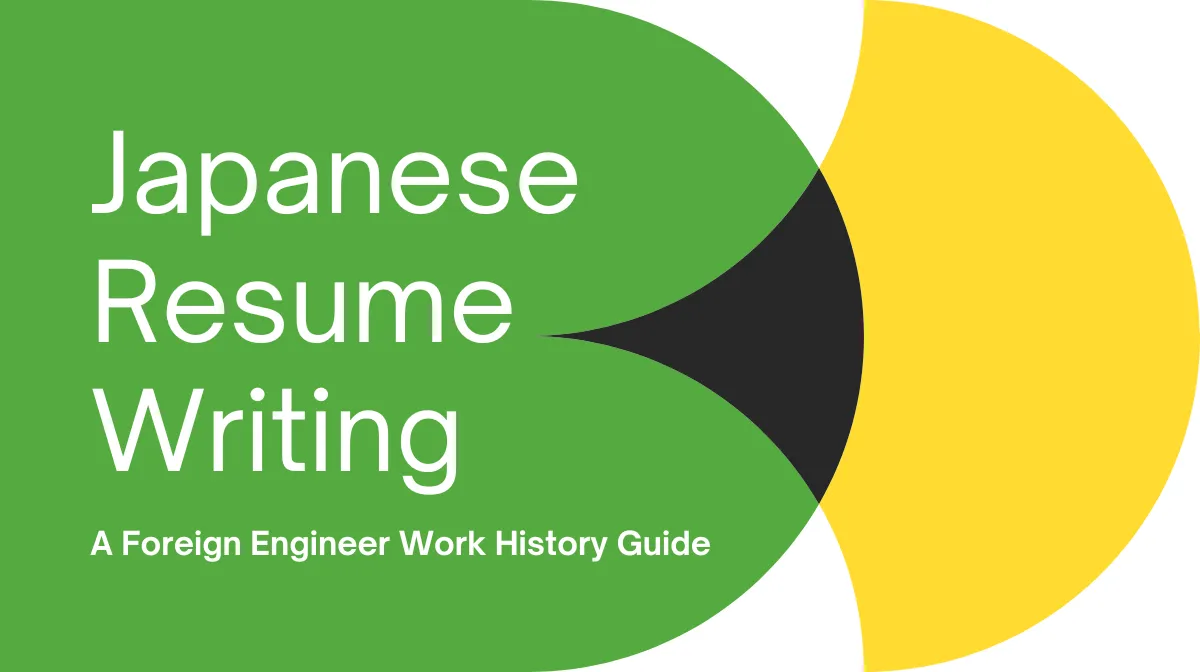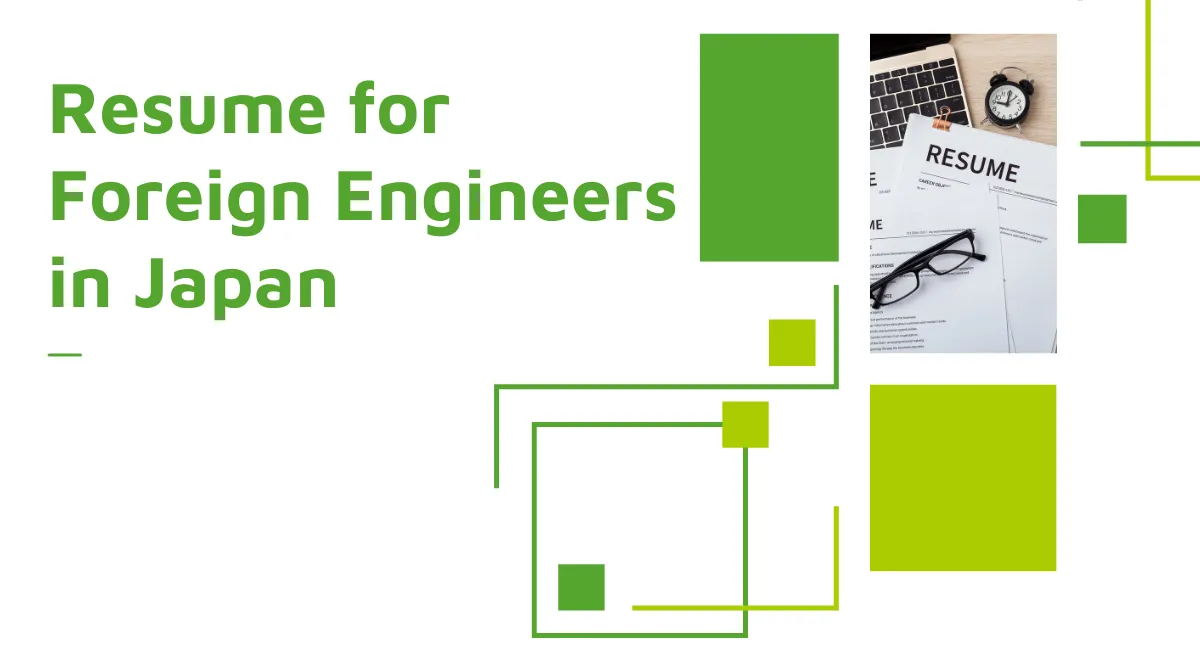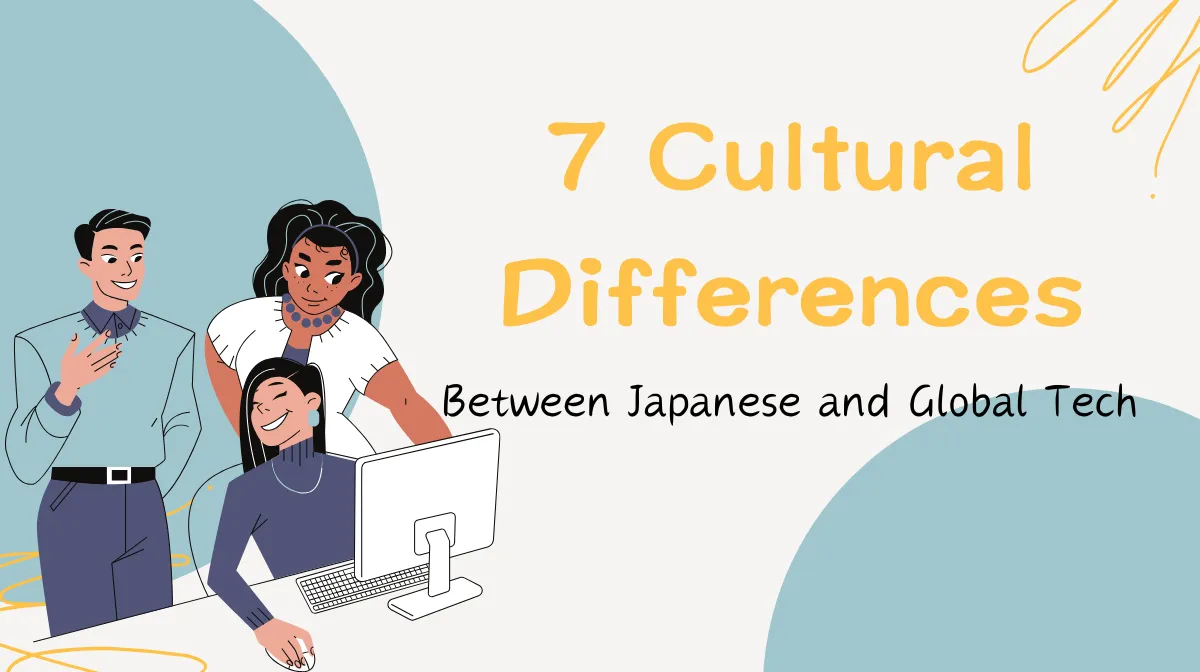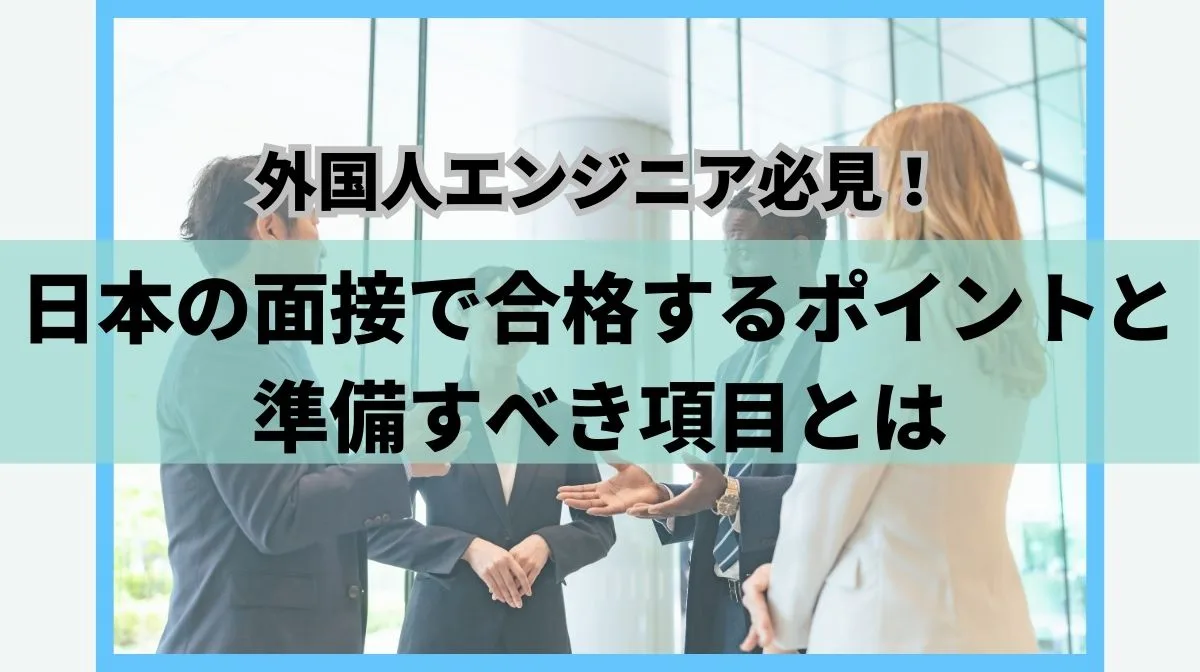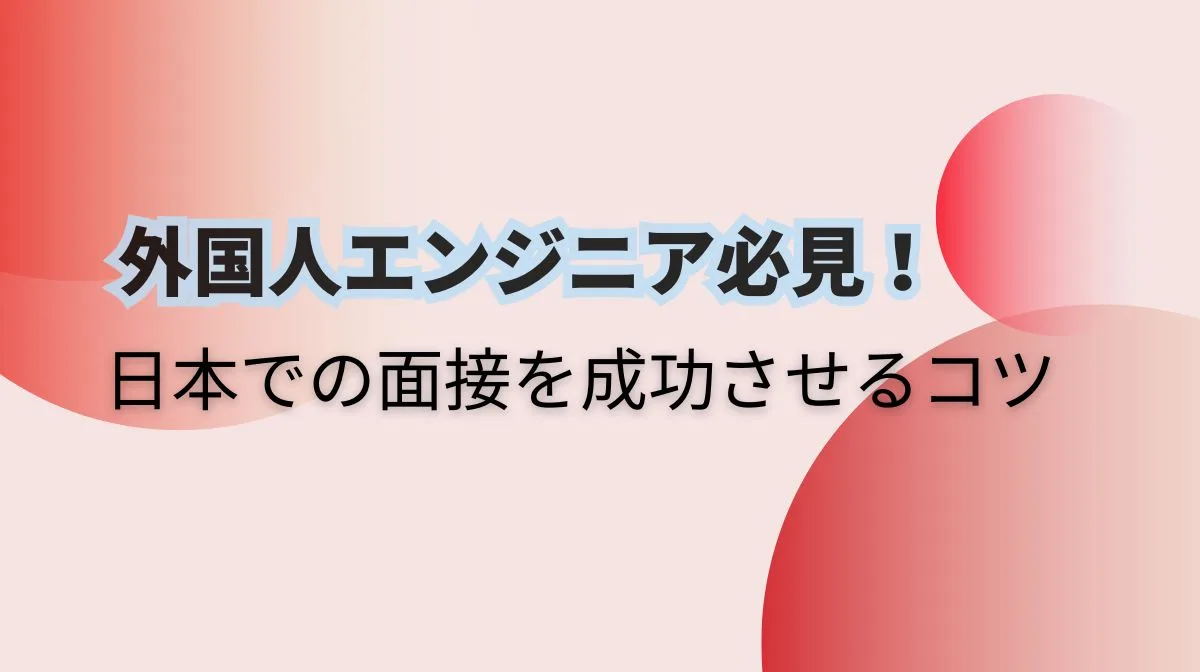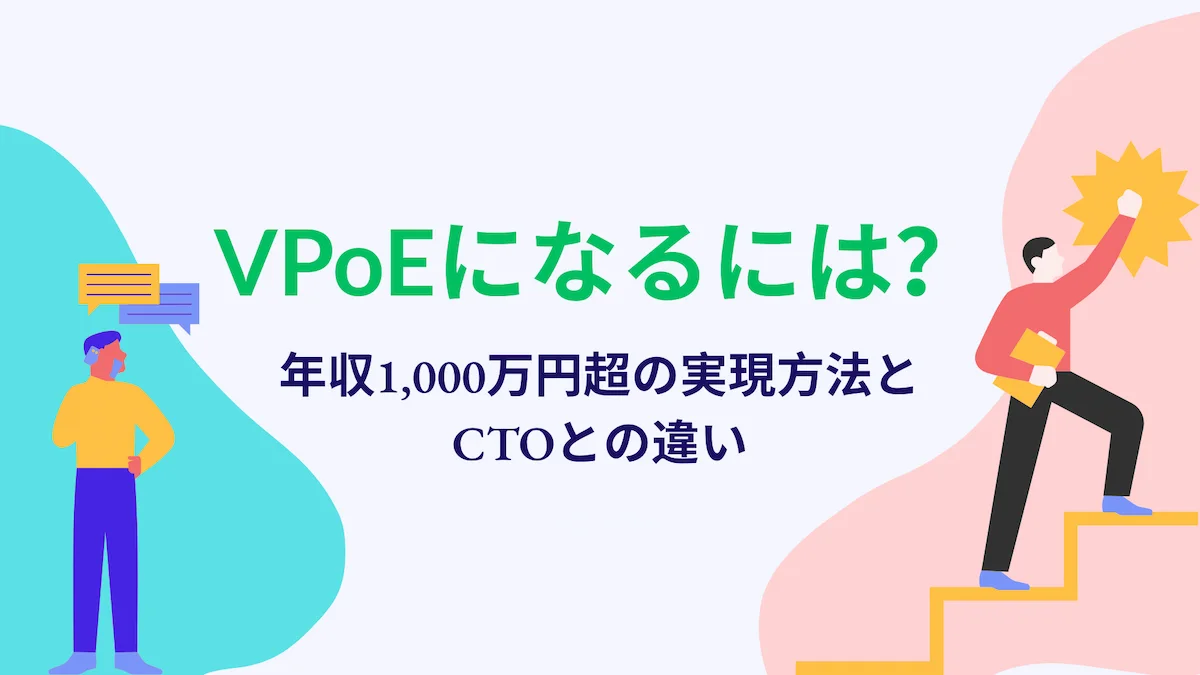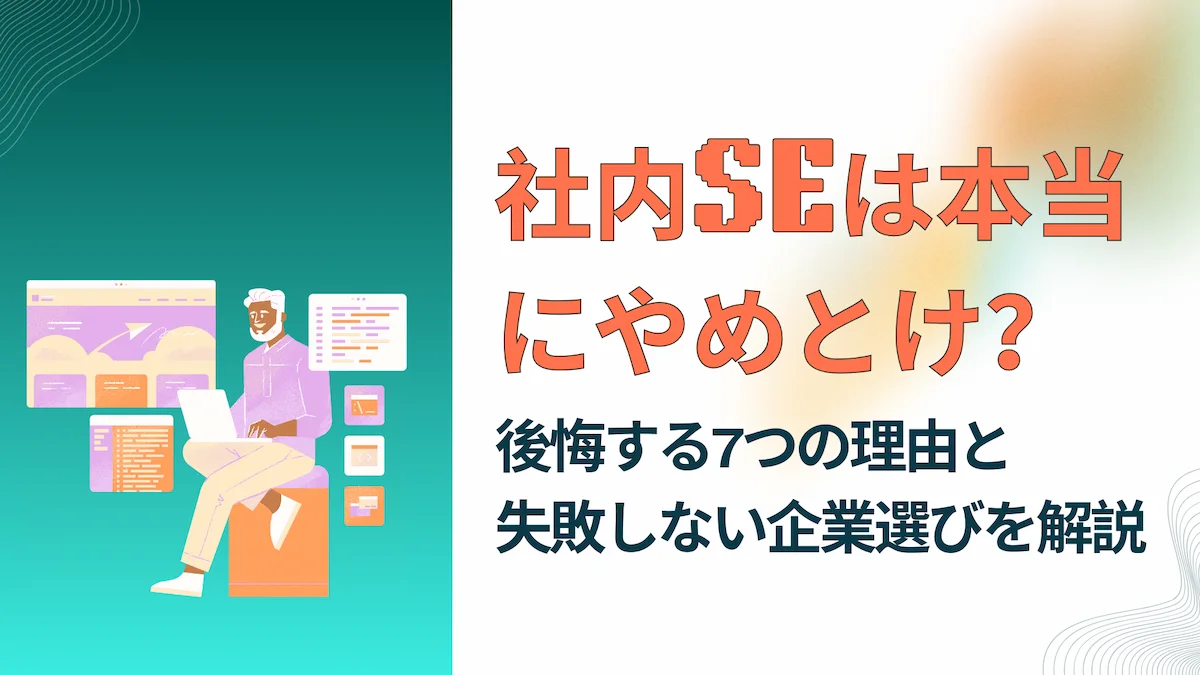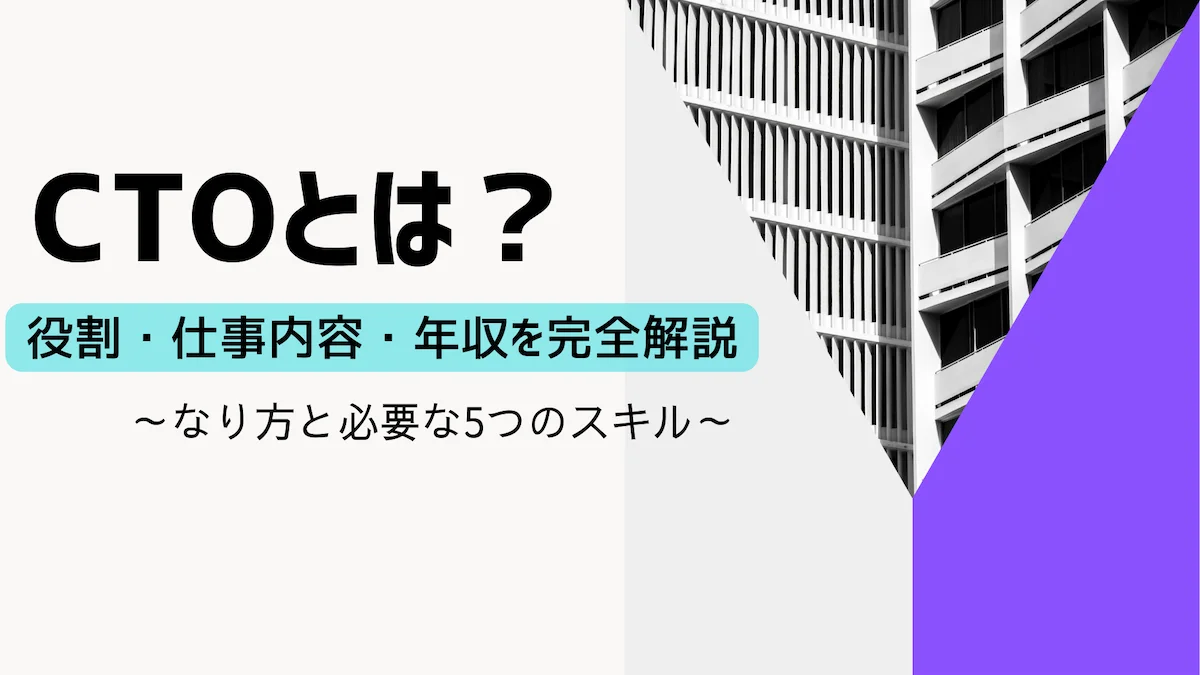日本の祝日は世界的に見ても多いことをご存知でしょうか?外国籍ITエンジニアにとって、日本の祝日を理解することは、効率的な休暇取得にもつながります。
本記事では、世界の祝日数ランキングにおける日本の位置づけなど、日本の祝日についてさまざまな角度から解説しています。
※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)
- 日本の祝日数とその特徴や欧米・アジア諸国との違い
- 日本と世界の祝日と、その背景にある歴史・文化的・社会的要因
- 外国籍ITエンジニアが日本で働く際に知っておくべき祝日関連の知識
1.日本の祝日はどのくらいある?

日本の祝日制度は世界的に見ても特徴的で、年間の休日数が多いことで知られています。
ここでは日本の祝日制度の基本的な特徴と仕組みについて解説します。
日本の祝日制度の基本的な特徴と仕組み
日本の祝日の大きな特徴は、自然との関わりを重視する祝日が多いことです。
春分の日・秋分の日は太陽と自然の循環を祝い、みどりの日は自然に親しむ日、海の日と山の日は自然の恵みに感謝する日となっています。
また、文化や歴史を尊重する祝日も充実しており、文化の日、建国記念の日、天皇誕生日などがあります。
日本独自の休暇パターン(大型連休の場合)
- ゴールデンウィーク(4月末~5月初旬)
- シルバーウィーク(9月の連休)
- 年末年始(12月29日~1月3日頃)
さらに「振替休日」という制度があり、祝日が日曜日と重なった場合は翌日の月曜日が休日となります。
外国籍ITエンジニアが日本の休日に抱く違和感
外国籍エンジニアにとって、日本の祝日システムには戸惑うことも多いでしょう。
まず、年間16〜17日という祝日数は、欧米(米国10日、英国8日、フランス9日など)と比較して非常に多く感じられます。
また、祝日が年間を通じて分散している点も特徴的で、欧米のようにクリスマスなど特定の時期に集中していません。
連休の取り方も異なり、欧米では2〜4週間の長期バカンスを取る文化がありますが、日本では連休を複数回に分けて取る傾向があります。
■合わせて読みたい
以下の記事では、日本企業で働くための労働・職場文化について、解説しています。
2.世界の祝日数ランキング:日本の位置は?

日本は世界的に見ても祝日が多い国として知られていますが、実際にはどのくらいの順位なのでしょうか?
ここでは世界各国との祝日数比較や、IT産業が盛んな国々の休日事情を分析し、日本の位置づけを明らかにします。
日本の位置付けとテック業界の休日事情
日本貿易振興機構(ジェトロ)のデータによると、日本の祝日数(振替休日を含む)は17日前後で推移しており、これは世界的に見てもトップ10に入る多さです。
| アメリカ…10日 | フランス…9日 | イギリス…8日 | ドイツ…9日 |
| 中国…11日 | シンガポール…11日 | 香港…13日 |
日本の休日事情は比較的恵まれており、一般的な企業の年間休日数は、完全週休2日制(土日)の104日に、祝日・振替休日の17~21日、年末年始休暇の3~7日、夏季休暇の3~5日、その他の1~3日を加えると、約128~140日になります。
世界のIT産業中心国の祝日数ランキング比較
世界のIT産業をリードする国々の祝日数を比較してみましょう。
- インド 21日
- イスラエル 18日
- 日本 17日
- 韓国 15日
- 中国 11日(春節など長期休暇期間除く)
- シンガポール 11日
- 米国 10日
- ドイツ 9日 フランス 9日
- 英国 8日
一般的に、アジア諸国(特に日本、インド)は祝日数が多いのに対し、欧米諸国は祝日数自体は少ないという傾向があります。
しかし、欧米諸国では祝日数は少ないものの、有給休暇の取得率が高く、長期のバカンスを取る文化があるため、総休暇日数では欧米が上回ることも多いのです。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
3.グローバルIT拠点との祝日比較

シリコンバレーやロンドン、シンガポールなど世界のIT産業の中心地と日本の祝日・休暇制度を比較します。
文化的背景の違いによる休暇の考え方や取得方法の差異に焦点を当て、外国籍エンジニアが知っておくべき各地域の特徴を紹介します。
米国(シリコンバレー、シアトル)vs日本(東京)の祝日と休暇制度
米国の主要テック拠点と東京を比較すると、米国の連邦祝日は10日で年初から分散していますが、11月〜12月に感謝祭やクリスマスなどが集中します。
多くのテック企業は年末年始に1〜2週間のクローズ期間も設けています。
一方、日本は17日前後の祝日があり、春(GW)と秋(シルバーウィーク)に連休が集中し、単発の祝日も多いのが特徴です。
欧州テック企業(ロンドン、ベルリン)と日本の違い
欧州のテック企業と日本を比較すると、イギリス(ロンドン)の祝日は8日、ドイツ(ベルリン)は9日(州により異なる)と日本より少なくなっています。
祝日を含めた休暇の取り方の文化も大きく異なります。欧州では「休むために働く」文化があり、夏季に2〜4週間の連続休暇が一般的です。
一方、日本では1週間以上の連続休暇は珍しいことも多いでしょう。
アジアIT先進国(シンガポール、インド、中国)との違い
アジア地域内でも国によって祝日制度は大きく異なります。シンガポールは11日の祝日があり、多文化・多宗教を反映した祝日が特徴です。
インドは21日前後(地域により異なる)で、ヒンドゥー教やイスラム教などの宗教的祝日が多いです。中国は11日の祝日に加え、春節(旧正月)や国慶節などで7日間程度の連休があります。
参考:日本貿易振興機構:シンガポールの祝祭日 :インドの祝祭日 :中国の祝祭日
4.祝日のあり方から見える各国の文化と価値観

祝日から、はその国の文化や歴史などがみえてきます。
ここではさまざまな国における祝日のあり方を知っていきましょう。
宗教的祝日と国家的祝日の国別バランス
祝日の設定は単なるカレンダー上の休みではなく、その国の価値観や歴史、文化を強く反映しています。その例としては、宗教的祝日や国家的・歴史的祝日のバランスがあげられます。
この比率を分析することで、各国の社会的特徴や価値観の優先順位が見えてきます。
<祝日タイプ別の国別分布>
- 日本: 国家的・歴史的(37%)、文化的(25%)、自然関連(19%)、労働関連(19%)、宗教的(0%)
- 米国: 国家的・歴史的(55%)、労働関連(18%)、宗教的(18%)、文化的(9%)
- ドイツ: 宗教的(67%)、国家的・歴史的(17%)、労働関連(8%)、文化的(8%)
- インド: 宗教的(57%)、国家的・歴史的(29%)、労働関連(14%)
- シンガポール: 宗教的(55%)、国家的・歴史的(27%)、労働関連(18%)
上記の分布から見えてくる最も顕著な特徴は、日本の祝日に宗教的要素がほとんど含まれていない点です。
欧州諸国(特にドイツやイタリア)
一方、欧州諸国、特にドイツやイタリアなどではキリスト教に関連する宗教的祝日が大半を占めています。イースター(復活祭)、クリスマスなど、キリスト教の重要な行事が祝日として定められています。
これらの国では宗教と国家の関係が日本よりも密接で、国民の日常生活や文化と宗教的要素が強く結びついていることを表しています。
アジア(シンガポール)
アジアでは、多宗教国家であるシンガポールの例が興味深いでしょう。
シンガポールは中国系、マレー系、インド系など多様な民族で構成される国家であり、祝日もそれを反映して、仏教・道教(旧正月)、イスラム教(ハリラヤプアサ、ハリラヤハジ)、ヒンドゥー教(ディーパバリ)、キリスト教(クリスマス)と、各主要宗教の祝日がバランスよく配置されています。
米国
米国の場合、独立記念日やサンクスギビングなど国家的・歴史的祝日が中心ですが、クリスマスやグッドフライデー(州によって異なる)などのキリスト教系の祝日も連邦あるいは州レベルで認められています。
国民の宗教的多様性を尊重しつつも、キリスト教的伝統も維持するというバランスを取っています。
インド
インドは宗教的多様性が非常に豊かな国であり、ヒンドゥー教の祝日だけでなく、イスラム教、キリスト教、仏教、ジャイナ教、シク教などの様々な宗教の祝日が国家的に認められています。
祝日設定に見る各国の歴史観と国民性
祝日は各国の歴史認識や国民性を映し出す鏡でもあります。どのような歴史的出来事を記念し、どのような価値観を祝うかは、その国の自己認識や理想を表しています。
<日本の祝日に見る歴史観と国民性>
日本の祝日には、戦後民主主義の価値観と伝統的な要素が混在しています。
「憲法記念日」(5月3日)日本国憲法の施行を祝うもので、「文化の日」(11月3日)も戦後の平和と文化国家を目指す理念が反映されています。
一方で「建国記念の日」(2月11日)や「天皇誕生日」は日本の伝統的な皇室と国家の歴史を尊重する姿勢を示しています。
また、日本の祝日は「春分の日」「秋分の日」など自然との調和を重視する独自の視点や、「敬老の日」「こどもの日」など家族や世代間の絆を大切にする価値観も表しています。
これらは日本人の自然観や社会観を反映したものといえるでしょう。
<米国の祝日と国家アイデンティティ>
米国の祝日は国家の形成と団結を祝うものが中心です。「独立記念日」(7月4日)は米国のアイデンティティの核心を祝い、「サンクスギビング」は開拓者の歴史を肯定的に位置づける祝日です。
「マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの日」や「追悼の日」(Memorial Day)は国の苦難の歴史と英雄を称える日となっています。
米国の祝日には愛国心と国家的物語の強調という特徴があり、国旗を掲げたりパレードを行ったりする公的な祝賀行事が盛んです。
<ヨーロッパ諸国の歴史認識と祝日>
ヨーロッパ諸国では国によって祝日の性格が大きく異なります。
フランスの「革命記念日」(7月14日)は市民革命の精神と共和制の価値を祝うもので、大規模な軍事パレードが行われます。
対照的にドイツでは第二次世界大戦後の反省から、ナショナリズムを強調する祝日は控えめで、「ドイツ統一の日」(10月3日)も比較的静かに祝われます。これは歴史と向き合う姿勢の違いを反映しています。
<ポストコロニアル諸国の独立記念日>
インドやアフリカ諸国など旧植民地諸国では「独立記念日」が最も重要な国家的祝日として位置づけられることが多く、国家形成の起点として祝われます。
インドの「独立記念日」(8月15日)や「共和国記念日」(1月26日)は壮大な式典で祝われ、国民統合の象徴となっています。
<多文化社会の祝日選択>
カナダやオーストラリアなどの移民国家では、様々な文化的背景を持つ市民を包含する祝日設定が課題となっています。
カナダでは先住民の日(6月21日)が祝われるようになり、オーストラリアでは「オーストラリアの日」(1月26日)の日付選択をめぐって先住民への配慮から議論が続いています。
<祝日の過ごし方に見る国民性>
祝日の過ごし方も国民性を反映します。日本のゴールデンウィークは旅行や消費活動が活発で、「ハレの日」として特別な活動をする傾向があります。
一方、フランスの8月のバカンスシーズンは多くの人が長期休暇を取り、都市から離れるという行動パターンが見られます。
米国のサンクスギビングは家族と過ごす日として重視され、感謝祭の夕食を囲む伝統が根付いています。
■合わせて読みたい
以下の記事では、日本企業で働くための労働・職場文化について、解説しています。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
5.日本で働く外国籍ITエンジニアが知っておくべき祝日の知識
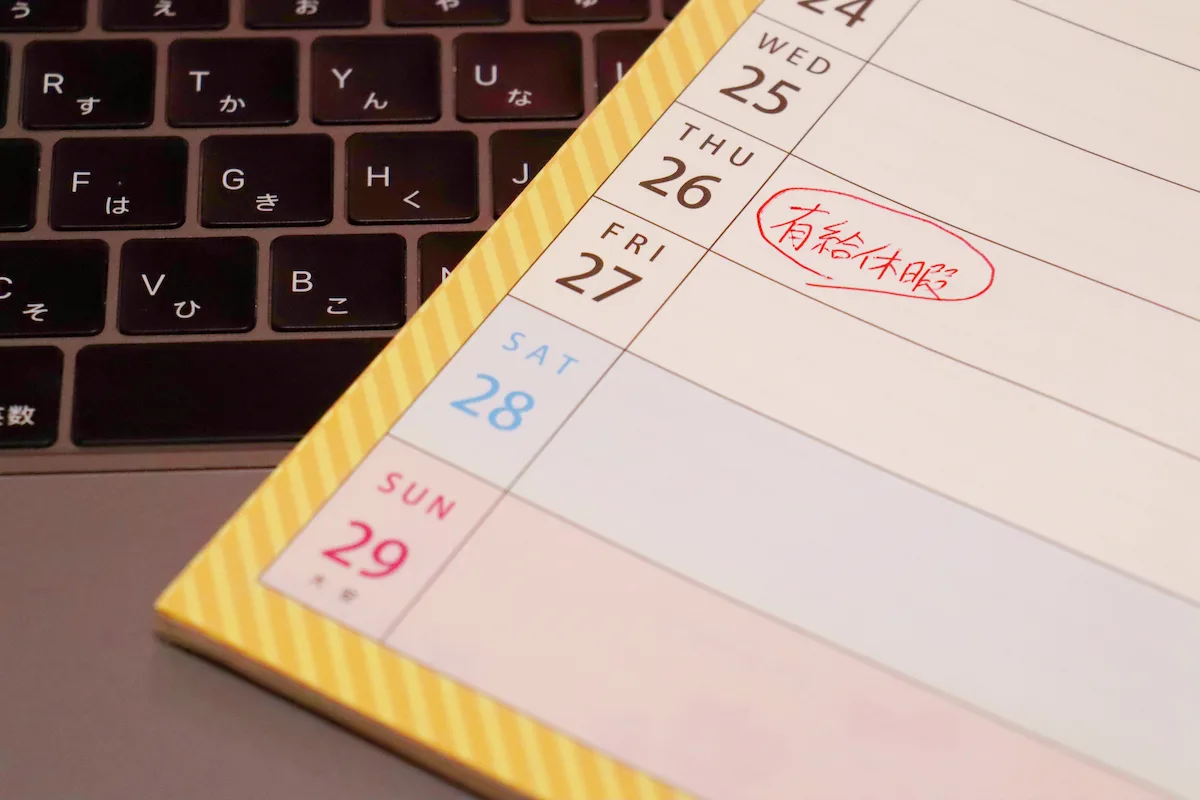
日本の祝日について知っておくことは、日本で働く上で役立ちます。日本特有の連休や祝日に関わるビジネス慣行などを理解することも重要です。
日本の「ゴールデンウィーク」「シルバーウィーク」とは
ゴールデンウィークは4月末から5月初めにかけての祝日が集中する期間で、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日で構成されています。
カレンダーの並び方によっては最大9〜10日の大型連休となります。
シルバーウィークは9月の敬老の日と秋分の日が近い日に配置される時に生じる連休で、数年に一度発生します。
外国籍エンジニアは計画的な予約の重要性、企業によるGW対応の違い、IT業界特有の連休対応、効果的な休暇活用法などに注意することが重要です。
祝日によって異なるビジネス慣行と注意点
日本では祝日の種類によってビジネスへの影響度が異なります。
最重要祝日期間(年末年始、GW)、重要祝日期間(お盆、シルバーウィーク)、中程度の影響(三連休)、軽度の影響(単独祝日)の4段階に分けられます。
祝日前後には「駆け込み現象」「事前準備メール」などの特有の慣行があります。
ITエンジニア特有の注意点としては、祝日前後のリリース回避、オンコール体制、プロジェクト計画での「祝日バッファ」の確保などがあります。
外国籍エンジニアは年間休暇カレンダーの把握、プロジェクト計画での祝日考慮、日本式休暇への適応などを心がけると良いでしょう。
6.2025-2026年の日本の祝日カレンダー

今後2年間の日本の祝日カレンダーを分析します。祝日について理解をしておくと、祝日を利用して休暇を取る場合なども便利です。
2025-2026年の祝日・連休パターン
2025年の総祝日数は17日(振替休日含む)です。
祝日活用のポイントとしては、2月の建国記念の日前日に有給取得で4連休、4〜5月GWは特定の平日に有給取得で最大11連休、9月の秋分の日前後に有給取得で4連休、9月〜10月にかけて5日間に有給取得で17日間の大型連休が可能です。
■2025年の主要連休
| 1月 | 元日と成人の日(最大4連休) |
| 2月 | 建国記念の日、天皇誕生日(最大3連休×2回) |
| 3月 | 春分の日(3連休) |
| 4〜5月 | GW(最大11連休) |
| 7月 | 海の日(3連休) |
| 8月 | 山の日(3連休) |
| 9月 | 敬老の日、秋分の日 |
| 10月 | スポーツの日(3連休) |
| 11月 | 文化の日、勤労感謝の日(3連休×2回) |
2026年も同様に17日の祝日があります。
季節別の長期休暇計画としては、春はGWを軸にした長期休暇が最も効率的、夏は7月の海の日と8月の山の日を活用し、秋は9月のシルバーウィークが最大の機会、冬は年末年始休暇を軸にクリスマスと組み合わせた長期休暇が可能です。
7.世界と日本の祝日の数を比較・理解すると「その国」がみえる

日本と世界の祝日制度には大きな違いがありますが、ITエンジニアとしてグローバルに活躍するには、これらの違いを理解し尊重することが重要です。
祝日数の多さだけでなく、異なる文化的背景など興味深い点が多くあります。祝日を知るとその国がみえてくると言っても過言ではないでしょう。
充実したワークライフバランスを実現するためにも、日本の祝日について知っておきましょう。