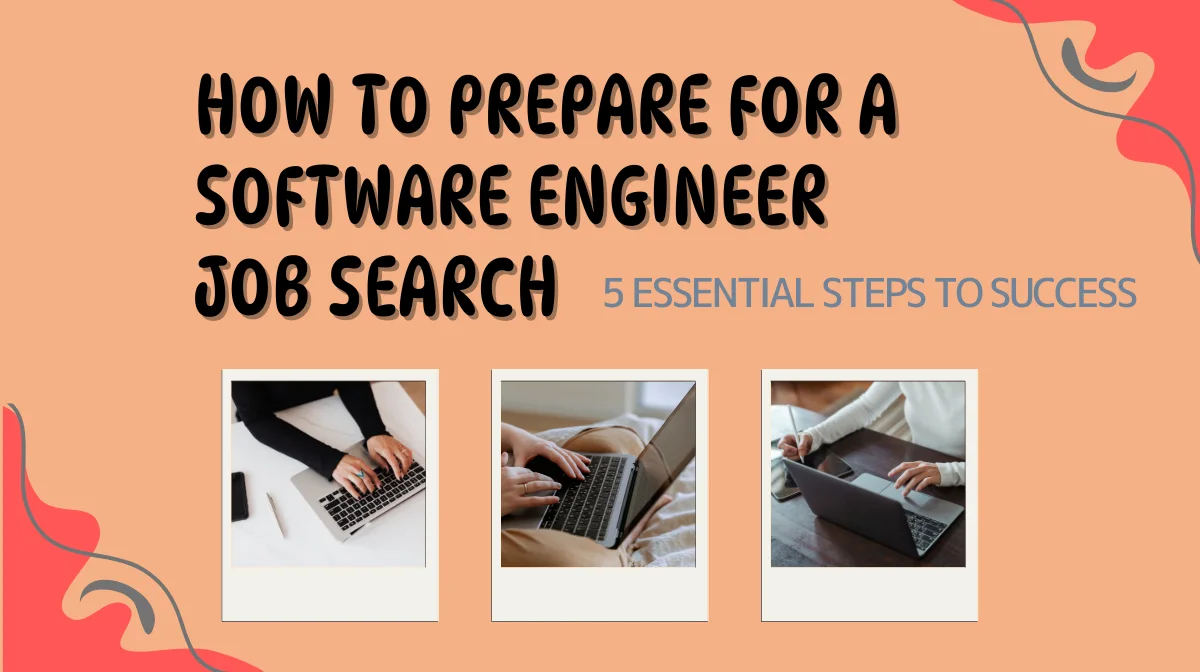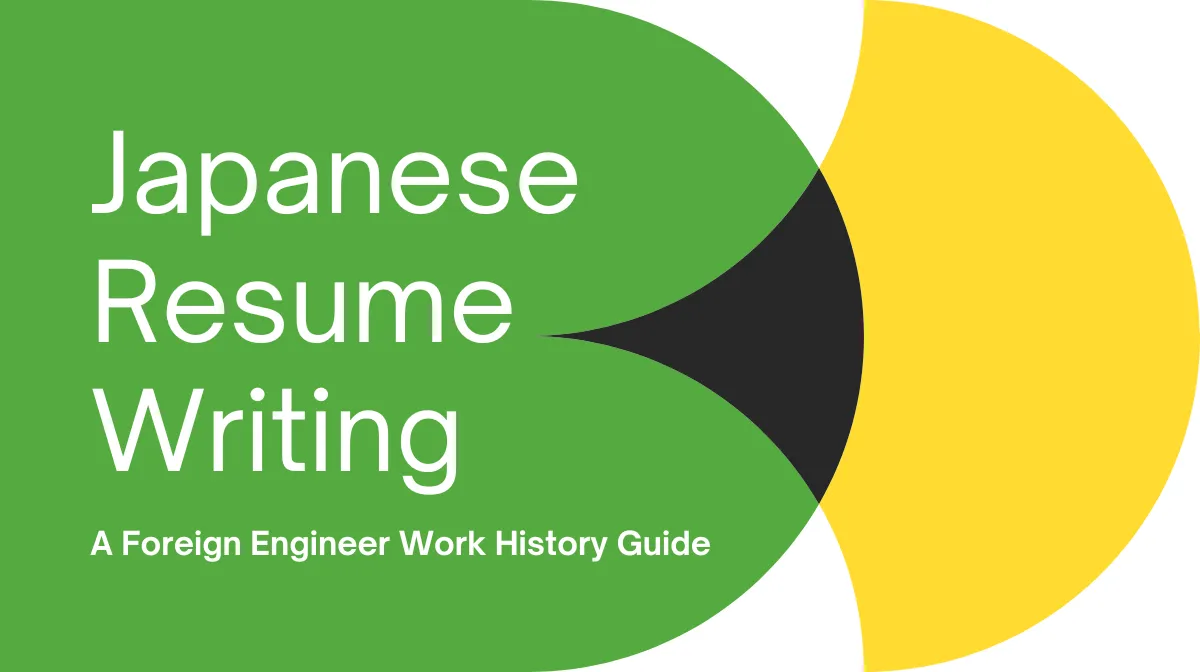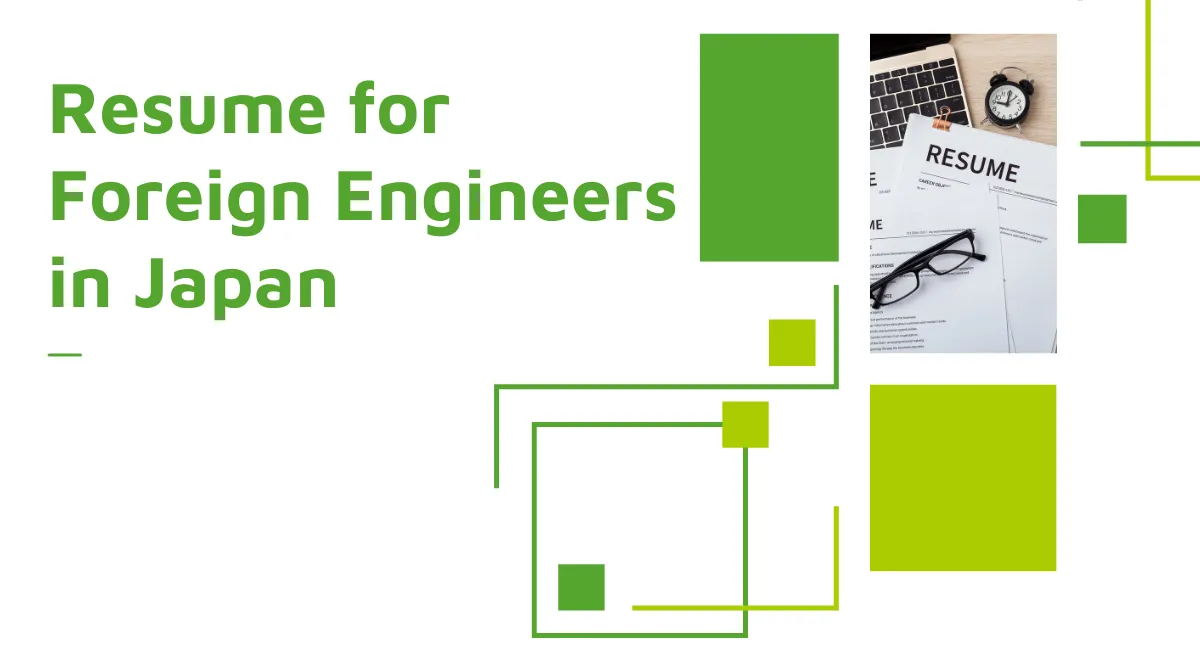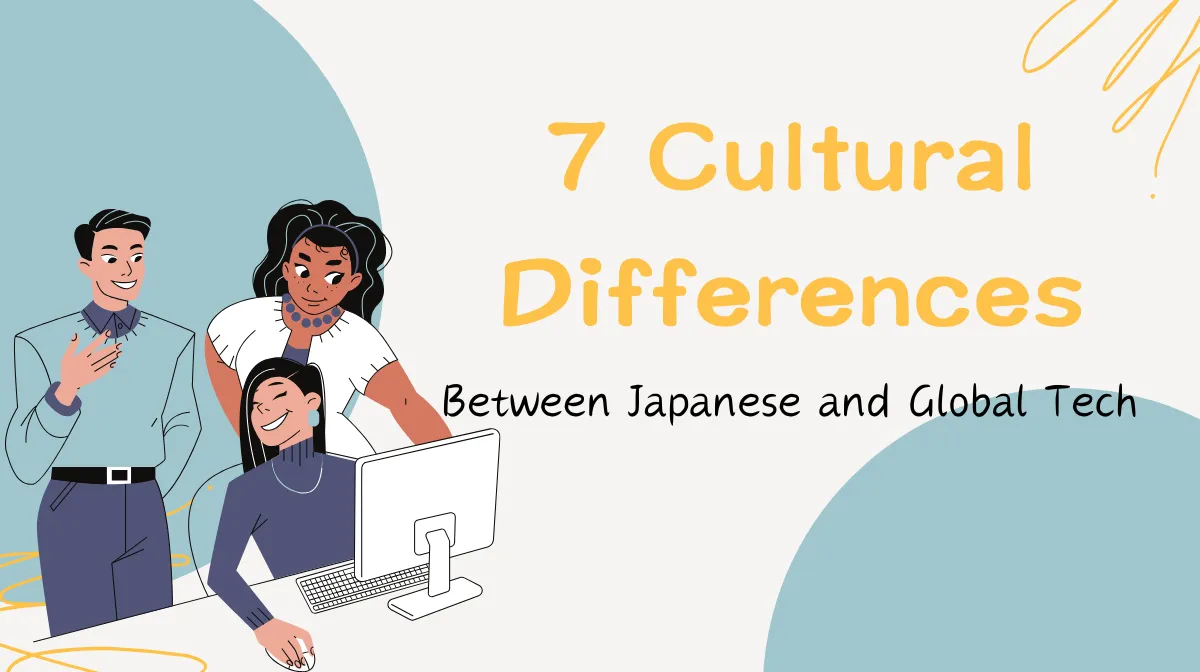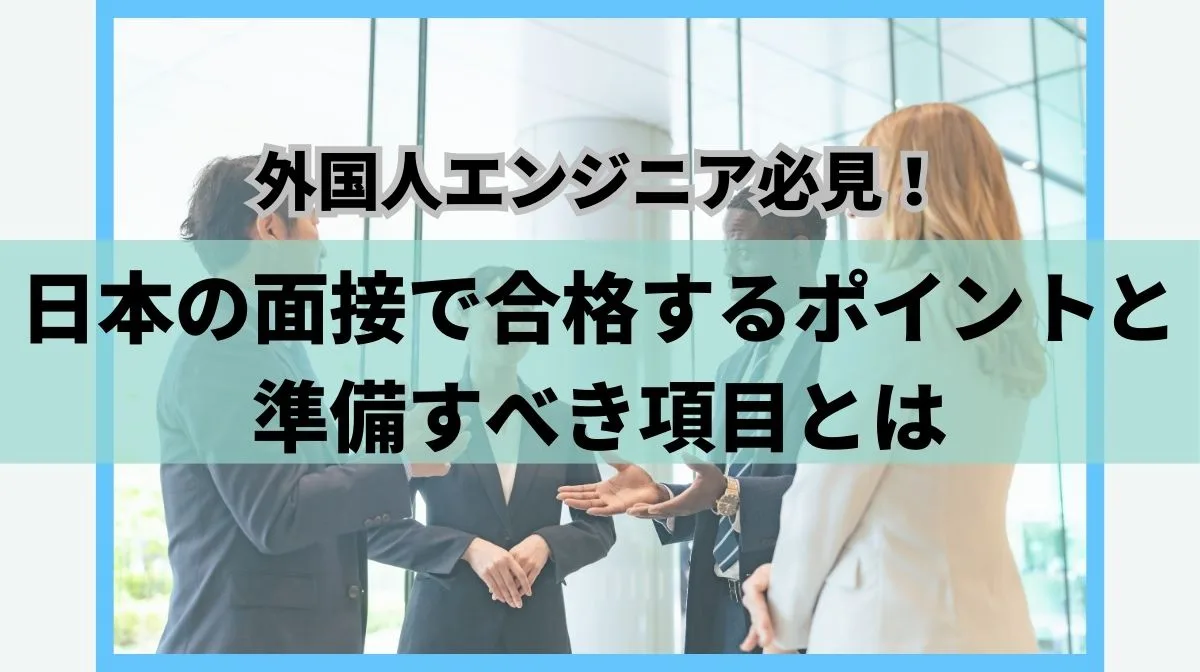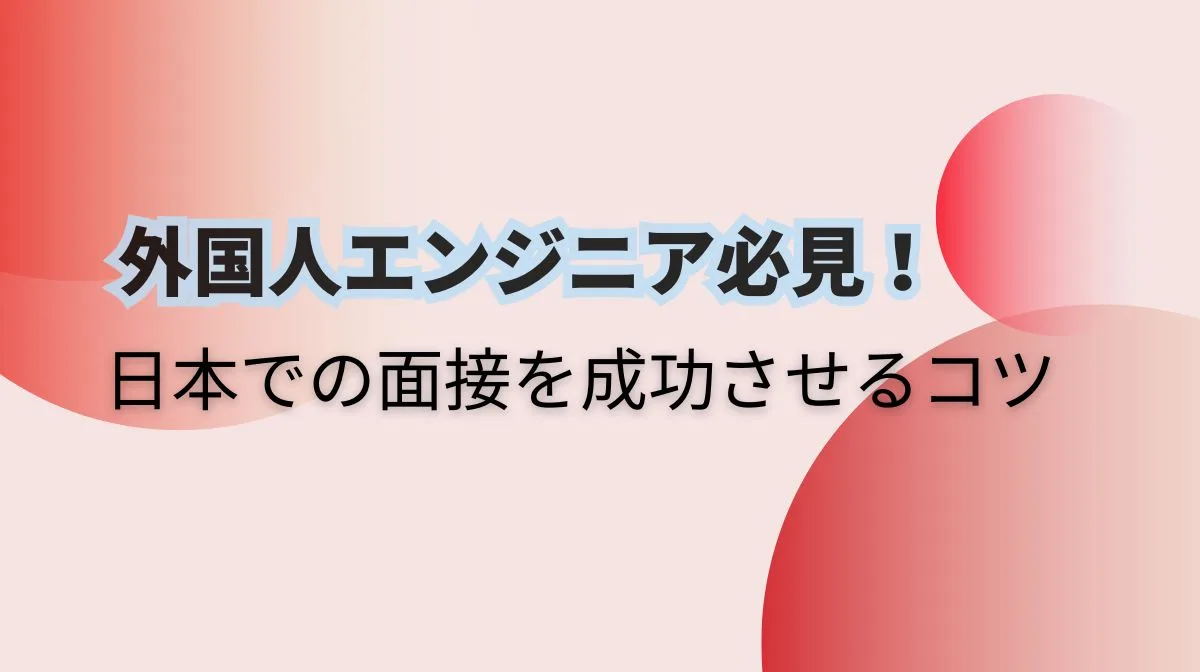エンジニアとして転職を考えているけれど、「何から始めればいいのか分からない」「準備不足で失敗したくない」と悩んでいませんか?
転職活動では準備の質が結果を大きく左右します。
この記事では、エンジニアの転職準備を5つのステップに分けて解説し、面接でやってしまいがちな失敗とその対策も紹介します。
※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)
- 転職準備の全体の流れと各ステップでやるべきことについて
- 職務経歴書の書き方と技術説明の具体的な方法について
- 面接でよくある5つの失敗とその対策について
1. エンジニアの転職準備で知っておくべき基本
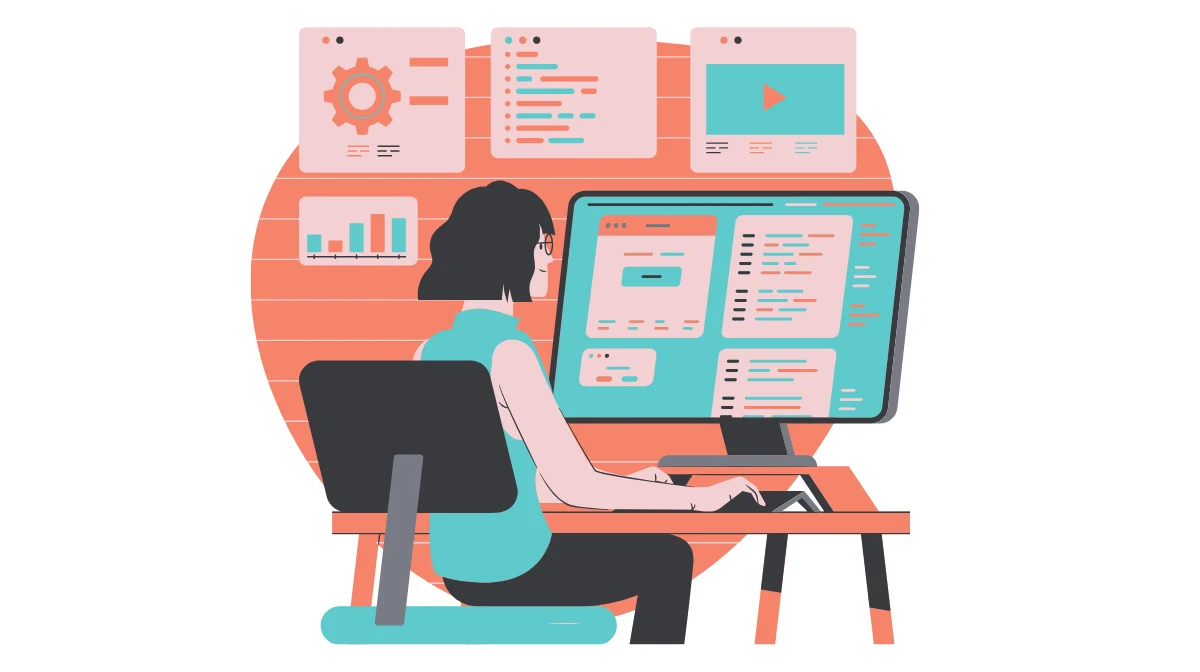
エンジニアの転職活動は、準備期間、活動期間、移行期間の3つのフェーズに分かれます。
全体で3〜6ヶ月程度かかるため、計画的に進めることが成功の鍵です。
ここでは転職準備の全体像と、働きながら転職活動を進めるべき理由を解説します。
転職準備の全体の流れ
エンジニアの転職活動は、大きく3つのフェーズに分かれます。全体で3〜6ヶ月程度の期間を見込んでおくと、焦らずに準備を進められます。
準備期間(1〜2ヶ月)
この期間では、転職の土台を作ります。自己分析で転職の目的を明確にし、職務経歴書やポートフォリオを作成します。
また、転職サイトへの登録や企業リサーチなど、情報収集も並行して進めます。
転職予定がなくても、職務経歴書は定期的に更新しておくと、いざという時にスムーズに動けます。
活動期間(2〜3ヶ月)
実際に求人に応募し、面接を受ける期間です。複数の企業に応募しながら、面接対策を繰り返しブラッシュアップしていきます。
この期間は特に時間管理が重要になるため、現職の業務と両立できるようスケジュールを工夫する必要があります。
移行期間(1〜2ヶ月)
内定を獲得した後、現職での退職手続きと引き継ぎを行います。退職の申し出は遅くとも1〜2ヶ月前には行い、円満退職を目指します。
入社日の調整や有給休暇の消化なども、この期間に計画的に進めましょう。
働きながら転職準備を進めるべき理由
転職活動は、退職してから始めるのではなく、働きながら進めることを強くおすすめします。その理由は主に3つあります。
収入を確保できる
転職活動には予想以上に時間がかかることがあります。
収入がない状態だと経済的なプレッシャーから焦りが生まれ、本来の希望とは異なる企業に妥協してしまう可能性があります。
キャリアに空白期間ができない
採用担当者は職歴の空白期間を気にする傾向があります。働きながらの転職であれば、この問題を回避できます。
焦らずに活動できる
現職を続けながらであれば、「転職しなければならない」というプレッシャーから解放され、冷静に企業を選べます。また、現職での状況が改善する可能性もあるため、転職するかどうかを柔軟に判断できます。
2. エンジニア転職準備のステップ1|自己分析と目標設定
不満をポジティブな目標に変換する
次の会社での具体的な業務や役割
5年後の理想のエンジニア像
言語、FW、クラウド等の習熟度を整理
役割、規模、期間、達成した成果を明確化
転職準備の最初のステップは自己分析です。なぜ転職したいのか、次の職場で何を実現したいのかを明確にすることで、企業選びや面接での説明に一貫性が生まれます。
ここでは転職理由の整理方法、スキルの棚卸し、年代別に求められる役割について解説します。
転職する理由と目的をはっきりさせる
転職活動を始める前に、以下の3つの質問に答えてみましょう。
なぜ転職したいのか?
現職への不満が転職のきっかけになることは自然です。ただし、面接では不満をそのまま伝えるのではなく、ポジティブな目標に言い換える必要があります。
例えば「残業が多い」という不満は「ワークライフバランスを保ちながら、効率的な開発環境で技術を磨きたい」という前向きな表現に変換できます。
次の会社で何をしたいのか?
転職先で実現したいことを具体的にイメージしましょう。
「最新の技術スタックに触れたい」「より大規模なシステム開発に携わりたい」「チームリーダーとしてマネジメント経験を積みたい」など、明確な目標があると企業とのミスマッチを防げます。
5年後どんなエンジニアになりたいか?
キャリアの方向性を考えることも重要です。特定の技術領域を深めるスペシャリスト志向か、幅広い技術を扱うゼネラリスト志向か。あるいは技術を極めるのか、マネジメントに進むのか。
長期的な視点を持つことで、今の転職が自分のキャリアにどう位置づけられるかが見えてきます。
自分のスキルと経験を整理する
職務経歴書を作成する前に、これまでの経験を棚卸ししましょう。
技術スキルの整理
プログラミング言語は実務で使用した年数と習熟度、フレームワーク・ライブラリはプロジェクトでの使用経験、インフラ・ツールはAWS、Docker、Git等の使用レベル、データベースは設計経験や最適化の実績などを書き出します。
プロジェクト経験の整理
どんなプロジェクトに参加したか(目的、規模、期間)、プロジェクトでの自分の役割(設計、実装、テスト、リーダー等)、プロジェクトで達成したこと(具体的な成果や改善実績)を明確にします。
この整理を通じて、自分の強みと弱みが見えてきます。不足しているスキルがあれば、転職前に独学や個人開発で補うことも検討しましょう。
年代別に求められるスキルを理解する
エンジニアの転職市場では、年代によって期待される役割が異なります。自分の年代で何が求められるかを理解し、それに合わせたアピールを準備しましょう。
20代前半
この年代では、基本的な技術スキルは前提となりますが、最も重視されるのは学習意欲とポテンシャルです。新しい技術を積極的に学ぶ姿勢や、ITへの強い興味関心を示すことが大切です。
経験が少なくても、個人開発やOSS貢献、技術ブログでのアウトプットなどで学習意欲をアピールできます。
20代後半〜30代前半
この年代では即戦力としての技術力が期待されます。一定以上の実務経験があり、入社後すぐにプロジェクトに貢献できることを示す必要があります。
また、数年後にはリーダーやマネジメント役割を担うことも想定されるため、チーム開発での貢献経験やメンバー育成の実績があればプラスになります。
30代後半〜40代
この年代では、専門的な技術力またはマネジメント経験が重視されます。
特定の技術領域で深い知見を持つスペシャリストか、プロジェクトやチームを率いた経験のあるマネジメント候補として評価されます。
プロジェクト全体を俯瞰する力や、技術選定・アーキテクチャ設計の経験などが強みになります。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
3. エンジニア転職準備のステップ2|職務経歴書の作成
職務経歴書はエンジニア転職で最も重要な書類です。面接官はこの書類を見て、あなたの技術力や経験を判断します。
ここでは職務経歴書に必ず書くべき内容、技術説明の具体的な書き方、成果を数字で表現する方法、ポートフォリオの活用法を解説します。
職務経歴書に必ず書くべき内容
職務経歴書には、職務要約、プロジェクト経験、技術スキル一覧、自己PRの4つの要素を必ず含めます。
職務要約(200〜300字)
これまでの経験を簡潔にまとめた概要です。どんな分野で何年程度の経験があるのかを端的に示します。
例:
「Web系企業で5年間、バックエンド開発を担当。ECサイトの決済システム開発や、マイクロサービス化プロジェクトに従事」のように、全体像が分かるように書きます。
プロジェクト経験
これが職務経歴書の中心部分です。
各プロジェクトについて、プロジェクトの目的と規模(何を作ったのか、チーム人数、期間)、自分の担当と役割(設計、実装、テスト、どの工程を担当したか)、使った技術(言語、フレームワーク、インフラ、ツール)、達成した成果(具体的な数字で示す)を記載します。
プロジェクトは新しいものから順に記載し、特に直近の経験を詳しく書きます。
技術スキル一覧
使える技術を一覧で示します。言語、フレームワーク、データベース、インフラ、ツールなど、カテゴリ別に整理すると見やすくなります。
それぞれのスキルについて、実務経験年数や習熟度を併記するとより効果的です。
自己PR
自分の強みと今後やりたいことを簡潔に記載します。
「新しい技術のキャッチアップが得意」「チーム開発でのコミュニケーションを大切にしている」など、技術力以外の強みもアピールポイントになります。
技術の説明は具体的に書く
エンジニアの職務経歴書で最も重要なのが、技術説明の解像度です。
技術に対してどこまで深い理解をしているかは、説明の具体性で判断されます。
NG例(悪い例)
「Javaができます」「AWSを使えます」「Webアプリを作りました」といった表現では、初心者も経験者も同じように見えてしまいます。
どのレベルまで使えるのか、何を実現したのかが全く分かりません。
OK例(良い例)
「Javaでモジュラーモノリスを設計・実装し、ドメイン駆動設計の原則に基づいてコードを構造化しました」
「AWS環境でKinesisとEventBridgeを使ってデータストリーミング処理基盤を構築し、リアルタイムデータ分析を実現しました」
「Reactを使って、月間10万ユーザーが使うECサイトのフロントエンドを開発しました。状態管理にはReduxを使用し、パフォーマンス最適化により初期表示時間を40%短縮しました」 など
具体的な技術用語を使い、何を実現したかを明確に示すことで、あなたの技術レベルが正確に伝わります。
成果は数字で表現する
プロジェクトでの成果は、できる限り数字で表現しましょう。定量的なデータがあると、あなたの貢献が具体的にイメージできます。
プロジェクト規模
チーム人数(5人チームでバックエンド開発を担当)、開発期間(6ヶ月間のプロジェクト)、予算規模(1,000万円のシステム開発案件)などを示します。
パフォーマンス改善
処理速度を50%向上させた、データベースクエリの最適化によりレスポンスタイムを2秒から0.5秒に短縮、メモリ使用量を30%削減といった具合です。
ビジネスインパクト
月間アクティブユーザー10万人のサービス、売上を前年比120%に向上させた機能開発、コスト削減により年間500万円の経費を削減などが挙げられます。
数字がない場合でも、「チームで最も多くの機能を実装」「プロジェクトの中核機能を担当」など、相対的な位置づけを示すことで貢献度を伝えられます。
ポートフォリオで技術力を見せる
職務経歴書だけでなく、ポートフォリオがあるとさらに説得力が増します。
GitHub
実際のコードを公開することで、コーディングスキルを直接アピールできます。個人開発のプロジェクトや、OSSへの貢献実績があれば、GitHubのURLを職務経歴書に記載しましょう。
READMEを充実させ、プロジェクトの目的や使用技術、工夫した点を説明しておくと、採用担当者が理解しやすくなります。
技術ブログ
QiitaやZennなどのプラットフォームで技術記事を書くことも有効です。学んだことをアウトプットする習慣は、継続的な学習姿勢の証明になります。
また、複雑な技術を分かりやすく説明する力は、チーム開発でのコミュニケーション能力の裏付けにもなります。
個人開発プロジェクト
実務では使っていない技術でも、個人開発で経験があれば強みになります。特に、モダンな技術スタックを使った個人プロジェクトは、新しい技術への興味と学習能力を示せます。
完成度よりも、「なぜこの技術を選んだのか」「どんな課題を解決したのか」を説明できることが重要です。
4. エンジニア転職準備のステップ3|企業リサーチと情報収集
転職準備では求人情報の収集と企業リサーチが欠かせません。複数の情報源を活用し、自分に合った企業を見つけることが重要です。
ここでは効率的な求人情報の探し方、転職サイトやエージェントの使い分け、応募企業の調査方法を詳しく解説します。
求人情報の探し方
求人情報を集める方法は主に3つあります。それぞれの特徴を理解して、効率的に活用しましょう。
エンジニア向け転職サイト
エンジニアに特化した転職サイトは、技術スタックや開発環境で検索できるのが大きな利点です。使いたい技術や興味のある分野をキーワードとして検索できるサイトがほとんどです。
また、企業の技術ブログや開発体制の情報が充実していることが多く、応募前に詳しく調べられます。複数のサイトに登録しておくと、より多くの求人情報にアクセスできます。
転職エージェント
転職エージェントを活用すると、非公開求人の紹介や面接対策のサポートを受けられます。特にエンジニア専門のエージェントは、技術的な知識を持った担当者が多く、的確なアドバイスをもらえます。
エージェントを選ぶ際は、エンジニア特化型を優先しましょう。担当者が技術に詳しくないと、希望とは異なる求人を紹介される可能性があります。
また、複数のエージェントに登録することで、より多くの選択肢が得られます。
その他の情報源
転職サイトやエージェント以外にも、LinkedIn、Wantedlyで企業の雰囲気や社員の声を知ることができます。
エンジニア勉強会やイベントは、connpassやTECH PLAYで探し、参加することで企業の技術レベルや文化を直接感じられます。
SNSでは、Xなどでエンジニアをフォローし、業界のトレンドや企業の評判を収集できます。様々な情報源を組み合わせることで、求人票だけでは分からない情報が得られます。
応募する会社を詳しく調べる
応募する前に、企業を徹底的にリサーチすることが重要です。
エンジニアは技術情報のリサーチに慣れているはずなのに、企業情報を調べていないのはリサーチ力に懸念があると判断されてしまいます。
技術面の調査
まず、その企業がどんな技術を使っているかを調べます。
- 使っている技術スタック(求人票に記載されている言語やフレームワーク)
- 開発環境(開発プロセス、使用ツール、インフラ構成)
- 企業の技術ブログ(どんな技術的課題に取り組んでいるか技術選定の理由など)、
- エンジニアの登壇資料(カンファレンスやイベントでの発表資料をチェックすると技術レベルが分かる)、
- GitHubアカウント(OSSを公開している企業もある)など
これらの情報から、その企業の技術的な成熟度や、自分のスキルが活かせるかを判断できます。
会社・組織の調査
技術面だけでなく、会社全体についても理解を深めます。
- 事業内容と将来性(どんなサービスを提供しているか、成長性はあるか)
- チーム構成と開発体制(チームの規模、開発の進め方、エンジニアの裁量)
- 会社の文化や働き方(リモートワークの可否、フレックス制度、残業時間)
- 社員インタビュー記事(実際に働いている人の声から、リアルな雰囲気が分かる)
企業のホームページ、技術ブログ、求人票は最低限読んでおきましょう。面接で「その企業でしか言えないこと」を話せるかどうかが、本気度の証明になります。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
5. エンジニア転職準備のステップ4|面接対策の実施
面接は転職活動の山場です。十分な準備をして自分の実力を正しく伝えることが内定獲得の鍵になります。
ここではエンジニア面接でよく聞かれる質問への回答準備、技術面接でのアピール方法、効果的な逆質問の作り方を解説します。
よく聞かれる質問の答えを準備する
エンジニアの面接では、以下の質問がよく聞かれます。事前に答えを準備しておくことで、落ち着いて対応できます。
自己紹介(30秒〜1分)
自己紹介は面接の第一印象を左右する重要な場面です。名前と現在の仕事、主なスキルと経験年数、得意な技術領域を含めて、簡潔にまとめましょう。
例
「○○と申します。現在はWeb系企業でバックエンドエンジニアとして5年間働いています。主にPythonとDjangoを使ったAPI開発を担当しており、マイクロサービスアーキテクチャの設計・実装が得意です。本日はよろしくお願いいたします」
上記のように、30秒から1分程度で話せるよう事前に練習しておきましょう。明るくはきはきと話すことで、コミュニケーション能力も評価されます。
転職理由と志望動機
転職理由 ネガティブな表現を避け、ポジティブな目標に変換して伝える
- NG例:「今の会社は古い技術しか使えないから」
- OK例:「モダンな技術スタックを使って、より高いレベルの開発に挑戦したいと考えています」
志望動機 その企業を選んだ具体的な理由を説明する
企業リサーチで得た情報を使い、「技術ブログで○○の取り組みを知り、共感した」「御社の△△という開発文化に魅力を感じた」など、その企業ならではの理由を述べましょう。
プロジェクト経験の説明
プロジェクト経験を説明する際は、STAR法を使うと分かりやすくなります。
- 状況(どんなプロジェクトだったか、背景は何か)
- タスク(自分に任された役割は何か)
- アクション(具体的に何をしたか、どう工夫したか)
- 結果(どんな成果が出たか、何を学んだか)
順序を追って詳しく説明することで、あなたの貢献が明確に伝わります。
技術面接でのアピール方法
技術面接では、技術力の深さと幅が評価されます。以下のポイントを意識してアピールしましょう。
担当範囲を正確に伝える
チーム開発では、どの工程をどれだけ担当したかを明確にします。「設計から実装、テストまで一貫して担当した」のか、「実装のみを担当した」のかでは、評価が変わります。
技術の深い理解を示す
単に「○○を使った」だけでなく、「なぜその技術を選んだのか」「どんな課題を解決したのか」「代替案と比較してどう判断したのか」まで説明できると、技術への深い理解が伝わります。
継続的な学習姿勢を見せる
実務では使っていなくても、個人で学習している技術があれば、それは継続的な学習姿勢の証明になります。
「最近はGoを勉強していて、個人プロジェクトでAPIサーバーを作りました」といった具体例があると効果的です。
逆質問を準備する
面接の最後には、「何か質問はありますか?」と聞かれることがほとんどです。
逆質問は、あなたの関心や意欲を示す重要な機会です。
良い質問の例
「チームの開発プロセスについて教えてください。スプリントの期間やレビューの進め方など」
「現在のチームで使っている技術スタックと、今後導入を検討している技術があれば教えてください」
「エンジニアのキャリアパスはどうなっていますか。技術を極める道とマネジメントに進む道、どちらも可能でしょうか」
「入社後、まず取り組むことになるプロジェクトについて教えていただけますか」
などが挙げられます。
避けるべき質問
企業のホームページを見れば分かること、給料や休日のことばかり聞く(条件面は大切ですが、技術的な質問とバランスを取りましょう)は避けましょう。
逆質問は3〜5個程度準備しておき、面接の流れで既に答えられた内容は除いて質問しましょう。
6. エンジニア転職準備のステップ5|スケジュールとタスク管理
転職活動を効率的に進めるにはスケジュール管理とタスク整理が欠かせません。特に働きながら転職活動をする場合、計画的に進めることが成功の鍵です。
ここでは転職活動全体のスケジュールの立て方、複数社応募時の管理方法、退職と引き継ぎの準備について解説します。
転職活動全体のスケジュールを立てる
転職活動のスケジュールは、入社したい時期から逆算して考えます。
6ヶ月計画の例
例えば、6ヶ月後に入社したい場合、1〜2ヶ月目は準備期間(職務経歴書作成、企業リサーチ、転職サイト登録)、3〜4ヶ月目は活動期間(応募、面接)、5〜6ヶ月目は移行期間(内定、退職手続き、引き継ぎ)というスケジュールになります。
プロジェクトの区切りを意識する
現職でプロジェクトを担当している場合は、プロジェクトの区切りで退職できるようにスケジュールを組むと、円満に退職しやすくなります。
また、現職の繁忙期と面接時期が重ならないよう調整することも大切です。忙しすぎて企業リサーチや面接対策が不十分なまま面接に臨むと、良い結果は得られません。
複数の会社に応募するときの管理方法
複数の企業に応募する場合、情報を整理して管理することが重要です。ToDo管理をどうするかは、転職準備の初期段階で整備しておくべきです。
管理すべき情報
応募した日、選考の段階(書類選考中、一次面接、二次面接、最終面接など)、面接の日時と場所(オンライン/オフライン)、提出した書類のバージョン(企業ごとにカスタマイズした内容)、面接で話したことのメモ(次の面接で一貫性を保つため)、企業からの連絡事項や締め切りなどを管理します。
おすすめの管理ツール
これらの情報を管理するツールとしては、Googleスプレッドシート(表形式で管理でき、どこからでもアクセス可能)、Notion(データベース機能を使って柔軟に管理できる)、Trello(カンバン形式で選考段階を視覚的に管理できる)などが便利です。
自分が使いやすいツールを選び、情報を一元管理しましょう。応募企業が増えると混乱しやすいので、こまめに更新することが大切です。
退職と引き継ぎの準備
内定を獲得したら、現職での退職手続きと引き継ぎを計画的に進めます。
退職の申し出タイミング
退職の申し出は1〜2ヶ月前が目安です。法律上は2週間前でも問題ありませんが、引き継ぎや後任の採用を考えると、余裕を持った期間が望ましいです。就業規則を確認し、規定がある場合はそれに従いましょう。
退職を伝える際
まず直属の上司に相談します。引き止められたり、待遇改善の提案をされることもあるかもしれませんが、転職の意思が固まっているなら、断固とした決意を伝えてください。
引き継ぎ内容の整理
引き継ぎでは、担当している業務の一覧、各業務の手順書やドキュメント、進行中のプロジェクトの状況、重要な連絡先や契約情報を整理します。
円満退職を目指すことで、将来的に元同僚から転職先を紹介してもらえることもあります。最後まで責任を持って業務を遂行しましょう。
また、有給休暇の消化計画も立てておきます。退職日と入社日の間に休息期間を設けることで、リフレッシュして新しい環境に臨めます。
7. エンジニアの転職準備でよくある失敗と対策

面接でやってしまいがちな失敗を事前に知っておくことで、同じ過ちを避けられます。
ここではエンジニアの転職面接でよくある5つの失敗パターンと、それぞれの具体的な対策方法を詳しく解説します。失敗例を理解して、万全の準備で面接に臨みましょう。
失敗1:経歴をダラダラ話してしまう
なぜダメか
面接官が知りたいのは「現時点での実力」です。昔の話や自慢話を長々と聞きたいわけではありません。時間が限られた面接で、関係のない経歴を話し続けると、本当に伝えるべきことが伝わらなくなります。
対策
今の実力を示すことに集中しましょう。過去の経歴は、現在の実力を説明するために必要な要素だけを簡潔にまとめます。
「何をやってきたか」よりも「今何ができるか」を明確に伝えることが重要です。
職務経歴書に詳しく書いてあれば、面接では要点だけを話し、面接官からの質問に答える形で深掘りしていく方が効果的です。
失敗2:成長する力が見えない
なぜダメか
企業は「現時点の実力」だけでなく、「将来の成長角度」も見ています。今のスキルだけを話して、これからどう成長するかが見えないと、将来性を疑問視されてしまいます。
対策
時間の経過で自分がどう成長したかを示しましょう。今後の成長意欲を具体的に伝えることが大切です。
例
「入社当初はフロントエンドのみでしたが、2年目からバックエンドも担当し、現在はフルスタックで開発できるようになりました」※時系列での変化を伝える
「最近はクラウドアーキテクチャに興味があり、AWS認定資格の取得に向けて勉強しています」※継続的に学んでいる姿勢を見せる
失敗3:技術の説明が曖昧
なぜダメか
技術に対する説明の解像度が粗いと、理解も粗いと判断されます。
「Javaができます」「AWSを使えます」といった曖昧な表現では、初心者もベテランも同じに見えてしまいます。
どこまで深く技術を理解しているかが分からず、採用側は判断に困ります。
対策
具体的で詳しい説明をしましょう。
「Javaでモジュラーモノリスとイミュータブルプログラミングを実施しました」
「KinesisやEventBridgeを使ってデータストリーミング処理やデータフローを作りました」 など
※具体的な技術用語を使って説明する
また、技術を選んだ理由や、他の選択肢と比較してどう判断したかも説明できると、さらに説得力が増します。
失敗4:転職理由がはっきりしない
なぜダメか
「なんとなく」「環境を変えたい」といったあやふやな印象をもたれるような理由では、採用されません。
なぜその会社を受けに来ているのか、面接している会社とやりたいことの説明にズレがあると、入社後のミスマッチにつながる可能性があります。
対策
明確な目標を持ち、志望する会社とのつながりを示しましょう。転職理由と志望動機は、一貫したストーリーになっている必要があります。
例
「現職では受託開発が中心ですが、自社サービス開発に携わりたいと考えています。御社の○○というサービスは、私が興味を持っている△△の領域で成長しており、そこで技術力を発揮したいと思いました」 など
※自分の目標と企業の特徴を結びつける
失敗5:応募する会社を調べていない
なぜダメか
エンジニアは技術情報のリサーチに慣れているはずです。
それなのに、応募する会社の情報をキャッチアップしていないのは、リサーチ力に懸念があると判断されます。また、本気で入社したいと思っているのか疑問視されてしまいます。
対策
最低限、企業のホームページ、技術ブログ、求人票は熟読しましょう。
可能であれば、使っている技術スタック、最近のプレスリリースやニュース、エンジニアの登壇資料や技術記事、社員のSNS投稿も調べておきます。
面接では「技術ブログで○○の記事を読みました」「最近△△のサービスをリリースされたと知りました」など、その企業でしか言えないことを話せるようにしましょう。
8. エンジニア転職準備でよくある質問

転職準備を進める中で多くの人が疑問に思うことをQ&A形式でまとめました。
転職準備を始めるタイミング、時間がない場合の対処法、職務経歴書のページ数、未経験分野への転職可能性、複数内定時の選び方など、実践的な質問に答えます。
転職準備はいつから始めればいいですか?
転職したい時期の3〜6ヶ月前から始めるのが理想的です。
準備期間、活動期間、移行期間を合わせると、最低でも3ヶ月は必要です。余裕を持って6ヶ月前から準備を始めると、焦らずに質の高い転職活動ができます。
ただし、転職予定がなくても、職務経歴書は定期的に更新しておくことをおすすめします。プロジェクトが終わるたびに経験を書き加えておくと、いざ転職を考えた時にスムーズに動けます。
働きながら転職準備をする時間がありません
時間の使い方を工夫すれば、働きながらでも転職準備は可能です。
の夜は1〜2時間を情報収集や求人チェック、応募書類の作成に充てます。
週末は3〜4時間を職務経歴書の作成や面接対策に集中します。面接は有給休暇やフレックスタイムを活用して調整しましょう。
また、転職エージェントを使うと、求人の紹介や企業とのやり取りを代行してもらえるため、時間を大幅に節約できます。
職務経歴書は何ページが適切ですか?
A4サイズで2〜3枚が目安です。
経験年数が少ない場合は1〜2枚、経験年数が多い場合は2〜3枚にまとめましょう。
長すぎると読まれない可能性があり、短すぎると経験が伝わりません。重要なのはページ数よりも内容です。
必要な情報を簡潔にまとめ、読みやすく整理することを心がけましょう。
未経験の技術領域に転職できますか?
年齢と準備次第で可能です。
20代であれば、ポテンシャル採用のチャンスがあります。学習意欲や成長可能性をアピールしましょう。
30代以降は、独学や個人開発で実績を作ることが重要です。実務経験がなくても、GitHubでコードを公開したり、個人プロジェクトで成果物を作ることで、技術力を証明できます。
また、完全に未経験ではなく、関連するスキルがあればそれをアピールしましょう。
複数内定が出たらどう選べばいいですか?
転職の軸に立ち返って判断しましょう。
自己分析で決めた「転職の目的」を思い出してください。技術成長、給与、働き方、企業文化など、自分が最も重視することを基準に比較します。
技術成長の機会、待遇、働き方、企業文化といった観点で比較すると判断しやすくなります。焦って決める必要はありません。内定承諾の期限延長が可能か相談し、じっくり検討しましょう。
9. 転職準備を整えてエンジニアとしての転職を成功させよう

エンジニアの転職を成功させるには、計画的な準備が欠かせません。
自己分析で転職の目的を明確にし、職務経歴書で技術力を正しく伝え、企業リサーチで応募先を深く理解し、面接対策で自分の実力をアピールし、スケジュール管理で効率的に活動を進める。
この5つのステップを順番に実行することで、転職活動はスムーズに進みます。
面接でよくある5つの失敗を事前に理解し対策を立てておくことも重要です。
転職は人生の大きな決断です。準備を万全にして、自信を持って理想のキャリアに向けた一歩を踏み出してください。