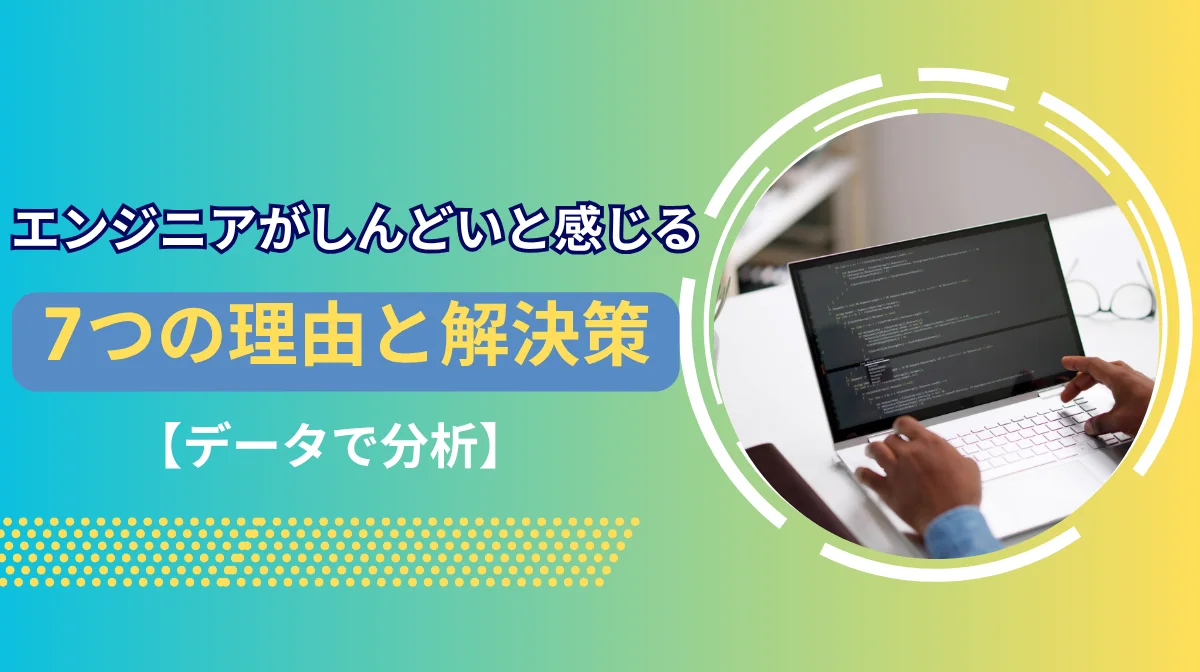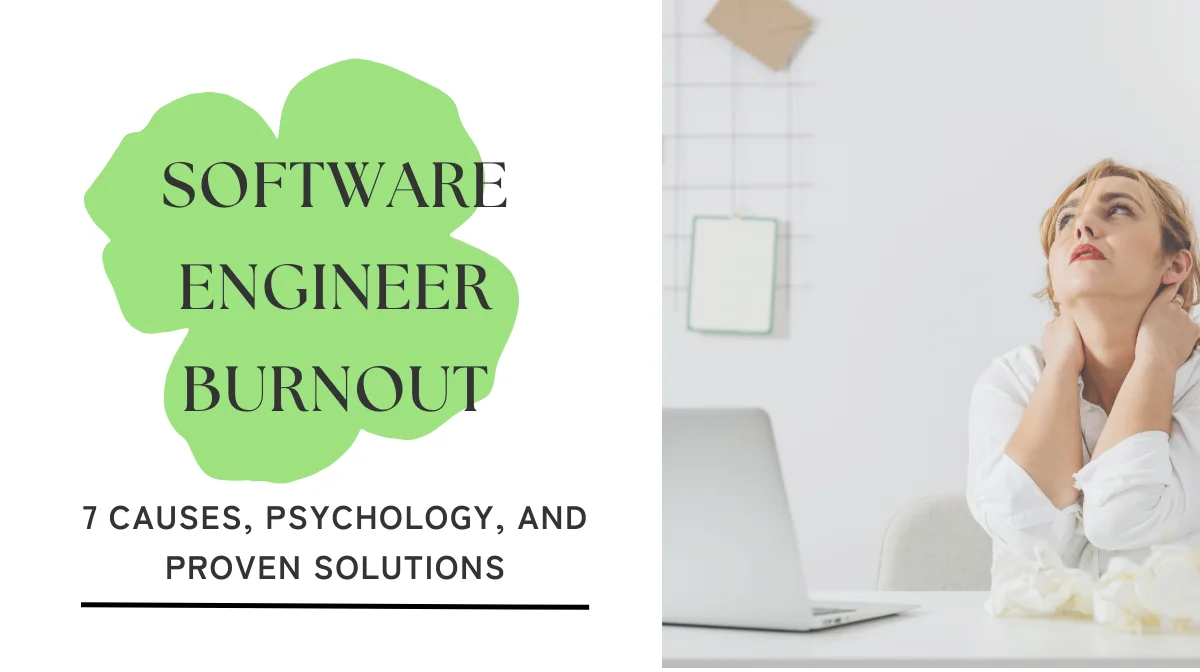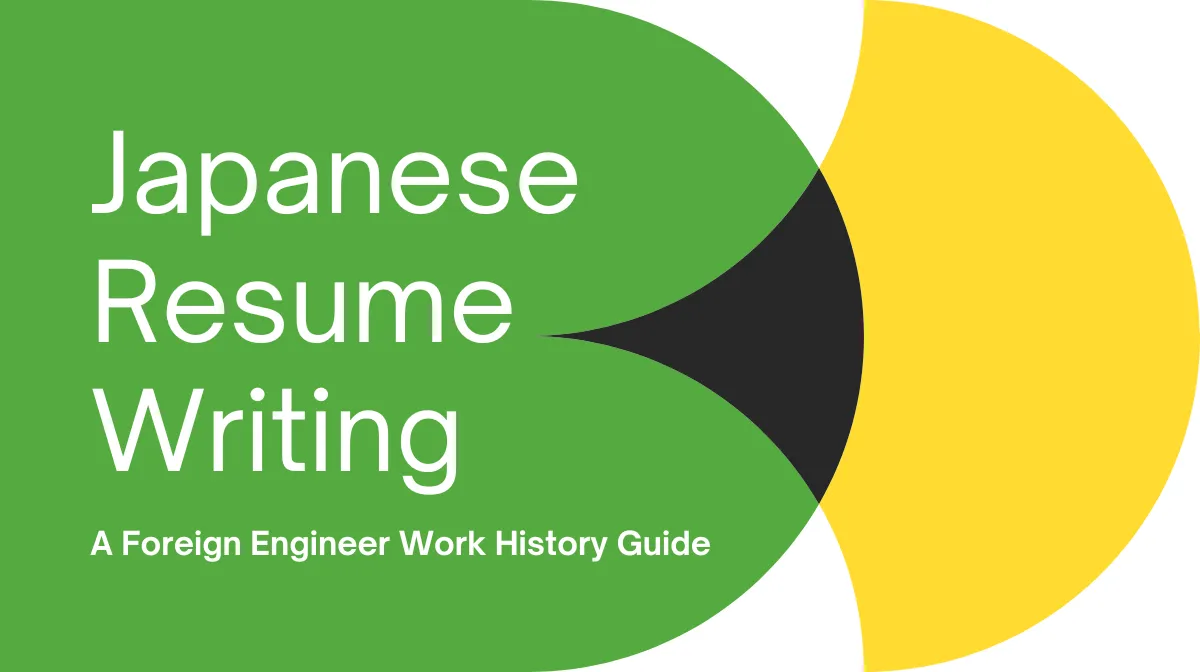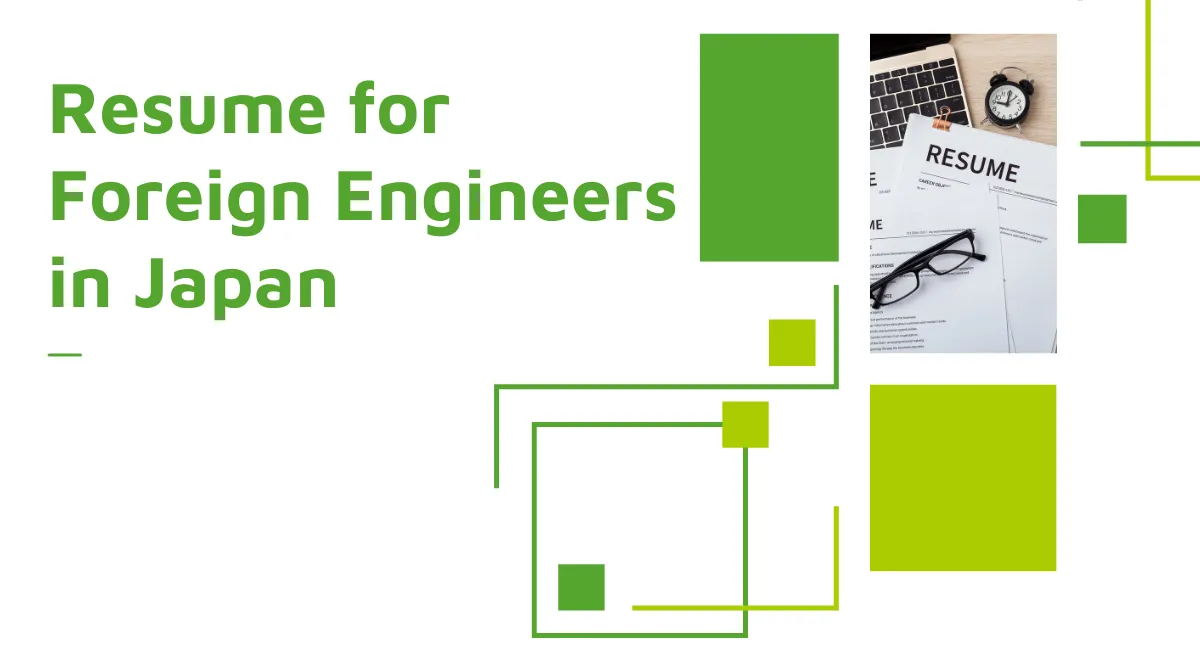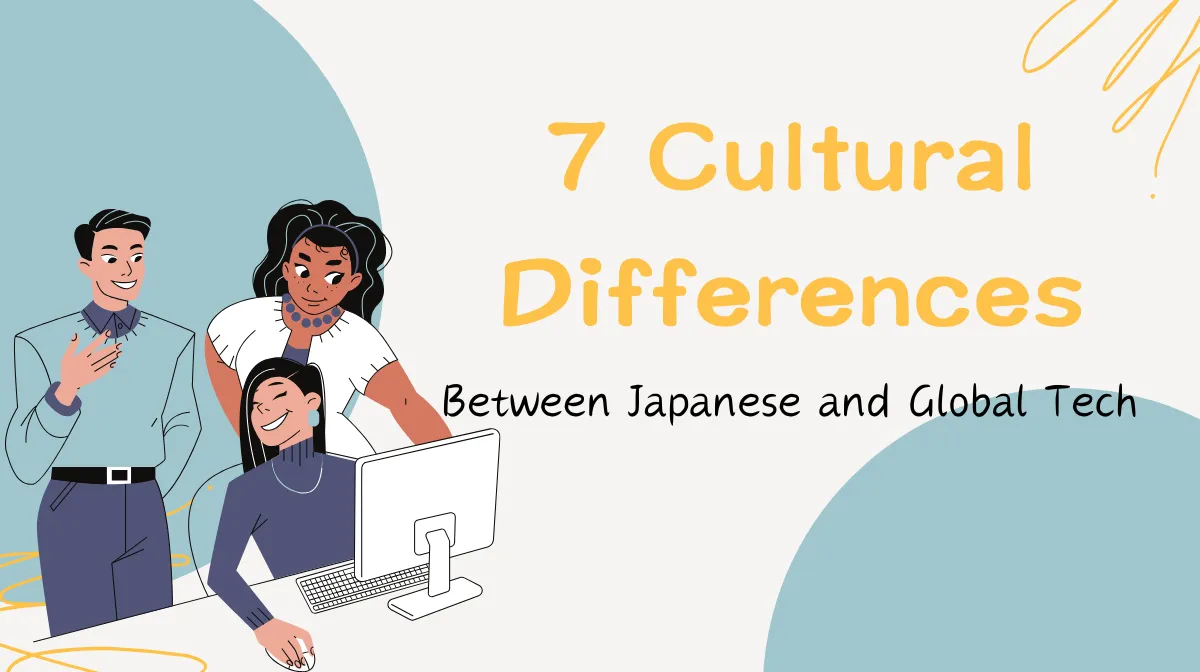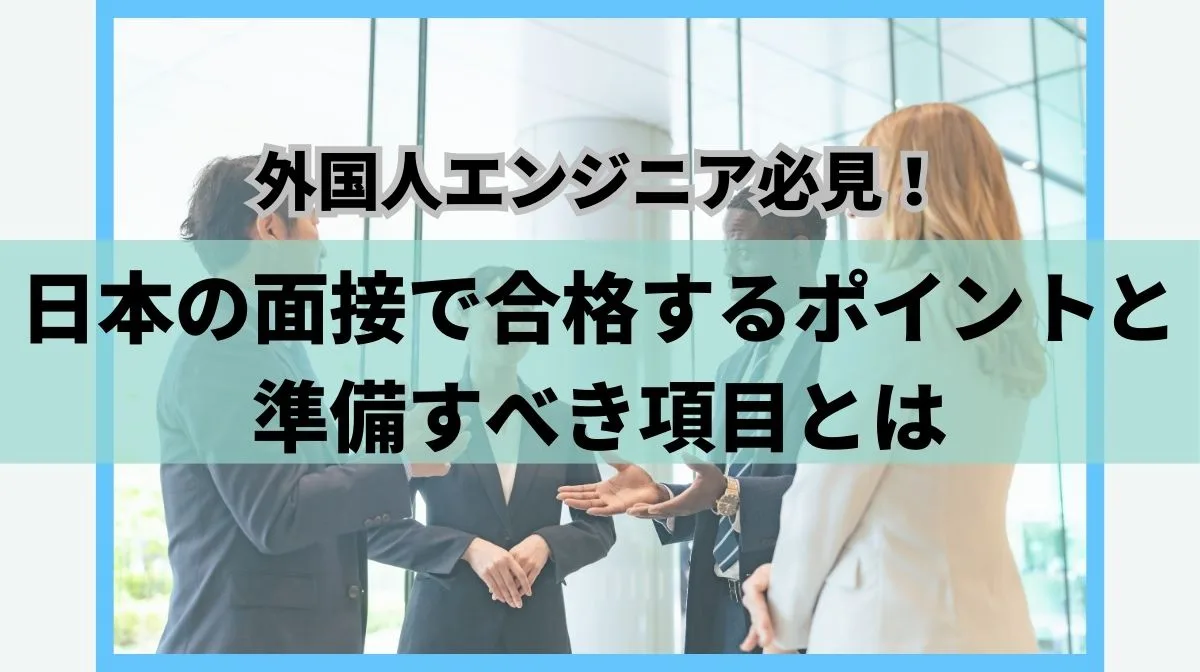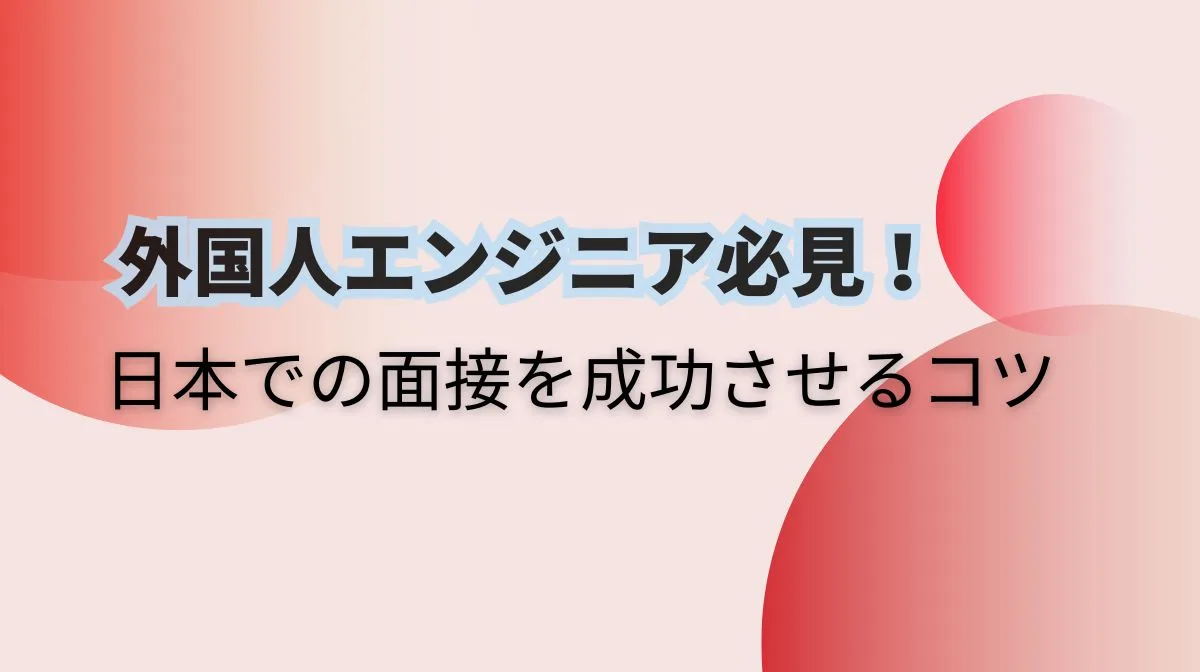エンジニアとして働く中で「最近、仕事がしんどい」「このまま続けていけるのか不安」と感じている方は少なくありません。
長時間労働、厳しい納期、絶え間ない技術キャッチアップ—これらの悩みは決して個人だけの問題ではありません。
この記事では、厚生労働省の調査データを基に、エンジニアが抱える「しんどさ」の実態を客観的に分析し、具体的な解決策をご紹介します。
※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)
- エンジニアの「しんどさ」が業界全体の構造的問題であることを示すデータについて
- 現職で今すぐ実践できる6つの改善策と転職成功のポイントについて
- AI時代でも価値を発揮し続けるための必須スキルと長期戦略について
1. エンジニアの「しんどい」は正当な悩み

多くのエンジニアが感じる「しんどさ」について、まず理解しておくべき重要な事実があります。
エンジニアの疲労感は甘えではない
厚生労働省の令和5年労働安全衛生調査によると、全業種において過去1年間にメンタルヘルス不調により1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.4%に達しています。
IT業界においては、特有のストレス要因により、この数値がさらに高い傾向があることが複数の調査で指摘されています。
エンジニア特有の困難が社会的に認知されるべき正当な課題であることを示す取り組みも増えており、業界全体でエンジニアのメンタルヘルス問題への理解が深まっています。
参考:厚生労働省「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)の概況」
2. エンジニアがしんどいと感じる現状をデータで把握
エンジニアの「しんどさ」を理解するため、業界全体の労働実態を客観的なデータで把握しましょう。
IT業界の労働実態:厚生労働省調査から見える真実
厚生労働省の「IT業界の働き方・休み方の推進調査」によると、IT業界において長時間労働を削減することが重要な課題であると位置づけられています。
労働時間を正確に把握するための制度の整備には積極的に取り組む企業が多い一方で、勤務間インターバル制度への取り組みはまだ積極的でない企業が多いという結果が出ています。
これは、労働時間の管理は進んでいるものの、労働者の実質的な休息確保には課題があることを示しています。
参考:厚生労働省「IT業界の働き方・休み方の推進|調査・分析結果」
残業時間の実態と不安の背景
ITエンジニアに特化した人材サービスを提供するGeeklyの2024年の調査では、全職種の月平均残業時間は21.0時間となっています。
しかし、IT業界においてはこの平均値を大きく上回るケースが多く報告されており、特にインフラコンサルタントでは39.4時間と、全体平均の約2倍の残業時間が記録されています。
また、ITエンジニアのキャリア不安の第1位が「自分の技術やスキルの陳腐化」であることが調査で明らかになっています。エンジニアが転職活動時に感じた不安で最も多かったのは「次の職場で上手くやっていけるか」でした。
これらのデータが示すのは、エンジニアの不安が単なる労働環境の問題だけでなく、技術の急速な進歩に追いつけるかという将来への不安や、自分の能力に対する自信の欠如という心理的な側面が大きいことです。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
3. エンジニアがしんどいと感じる本当の理由7選
エンジニアの「しんどさ」の背後には、業界特有の構造的問題と個人的な心理的要因が複雑に絡み合っています。
長時間労働と休日出勤
ITエンジニアの残業時間は他業種と比べて突出して多い傾向があります。特に深刻なケースでは、月150時間の残業が連続するような状況も報告されています。
この背景には、エンジニアの仕事が「成果物を納品することで完了する」という特性があり、納期は絶対的であり、どのような状況であっても期日までに納品する責任が重くのしかかります。
厳しい納期とプレッシャー
エンジニアの仕事では、納期遅延が損害賠償などの大きなトラブルに繋がるケースがあるため、「何が何でも間に合わせなければならない」という重圧が常につきまといます。
開発プロジェクトでは想定外の事態が日常的に発生し、その度にエンジニアは「解決するまで帰れない」状況に追い込まれます。
「納期のプレッシャーがないことなんてない。エンジニアをやっている以上は一生付き合っていくもの」という声もいまだに多く、業界全体の課題となっています。
絶え間ない技術キャッチアップ
「エンジニアは一生勉強し続けなければならない」という業界の常識が、多くのエンジニアに重い心理的負担をかけています。IT業界では「半年前の技術トレンドがもう古い」という状況が珍しくありません。
実際のエンジニアの証言では、「毎週のように新しい技術に出くわす」「キャッチアップ→習得→実装という流れを何度も高速で繰り返さなければならない」という状況が報告されています。
この学習圧力は平日の業務時間外や休日にも及び、仕事と学習の境界が曖昧になり、真の意味での休息時間を確保できないエンジニアが多数存在しています。
正当な評価を受けられない
技術的な成果は目に見えにくく、システムの安定稼働やパフォーマンス改善、セキュリティ強化といった重要な貢献が、営業成績のような数値として明確に表れないため、適切に評価されないケースが多発しています。
ITエンジニアは他の職種と比較して組織への批判的態度が転職意向に顕著につながりやすく、転職理由の第1位が「収入アップのため」となっていることからも、この問題の深刻さが伺えます。
人間関係とコミュニケーション
深刻な問題の一つが「客先常駐」という働き方です。
メンタルヘルス疾患で1ヵ月以上休職し復職したITエンジニアを対象とした調査では、メンタル不調のきっかけとなった時期は、いずれも客先常駐の環境下にあったことが明らかになっています。
また、エンジニアと非エンジニアとの間には、技術的な知識レベルや思考プロセスの違いから、コミュニケーションギャップが生じやすい傾向があります。
技術的な課題や制約を説明しても理解されない、無理な要求を受けるといった状況が頻繁に発生し、これがストレスの原因となります。
将来への不安:AI時代における価値への疑問
「4年以内に業務の半分以上がAIに代替される」と予測するエンジニアが35.2%に達していると言われています。
ITエンジニアのキャリア不安の第1位が「自分の技術やスキルの陳腐化」となっており、技術の進歩によって自分の価値が失われることへの恐怖が最大の心配事であることが明らかになっています。
コード生成AIの登場により、簡単なプログラミング作業の自動化が進んでおり、従来のエンジニアの業務領域が侵食されつつあります。
やりがいとのミスマッチ
多くのエンジニアが「新しい技術で世界を変えたい」「革新的なサービスを作りたい」といった高い理想を抱いています。
しかし、実際の業務では、レガシーシステムの保守・運用、繰り返しの多い作業、技術的に挑戦的ではない案件が大部分を占めることが珍しくありません。
特に多重下請け構造の下位に位置する企業では、上流工程の設計や企画に関わることができず、単純作業的なコーディングやテスト作業に従事することが多くなります。
4. エンジニアのしんどさの背景にある深層心理
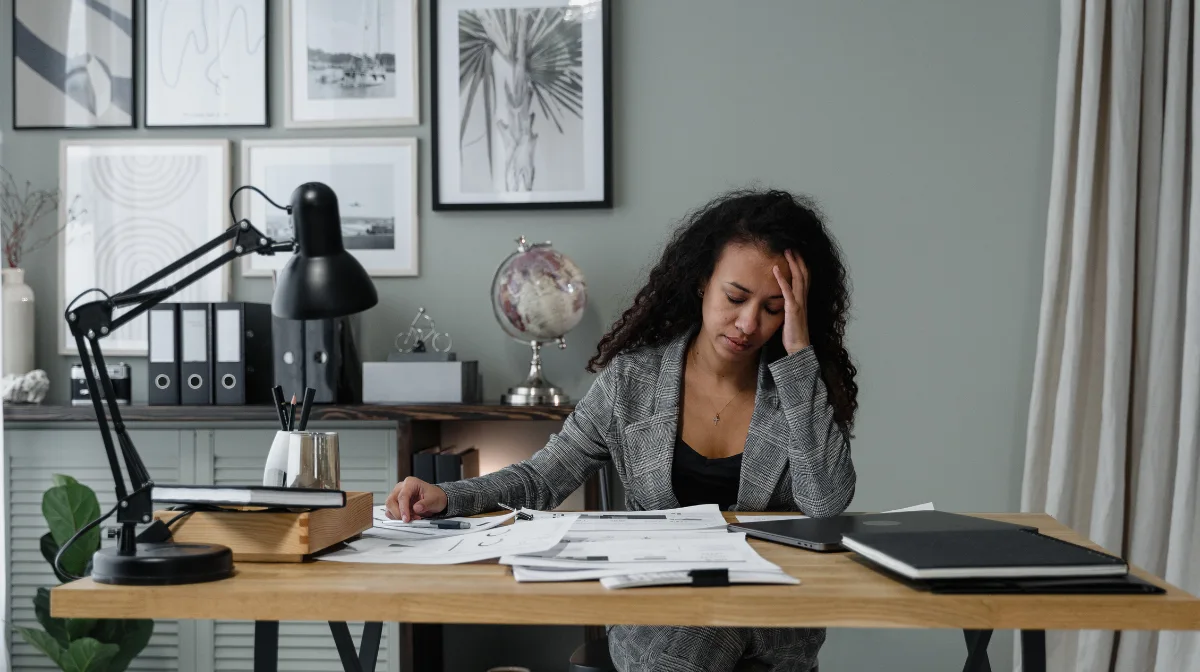
エンジニアが感じる「しんどさ」の背後には、職業特有の心理的特性と社会的要因が複雑に絡み合っています。
完璧主義による自己否定のループ
エンジニアの仕事は本質的に「これ以上やることはない」という明確なゴールが見えにくい性質を持っています。
プロ意識が高く技術への情熱を持つエンジニアほど、「もっと良くできるはず」という思考が止まらなくなると、作業に終わりが見えなくなり、結果的に長時間労働や精神的な疲労に繋がってしまいます。
完璧主義者は理想の自分と現実の間に大きなギャップを感じやすく、客観的には優秀な成果を上げていても「まだ十分ではない」と感じ、自己否定に陥りやすくなります。
インポスター症候群:「自分は偽物だ」という思い込み
エンジニア業界で特に多く見られる心理的な問題が「インポスター症候群」です。
これは、実際には能力があり周囲から高い評価を受けているにも関わらず、「自分は偽物だ」「周囲を騙している」と感じてしまう心理状態を指します。
この症候群がエンジニアに特に多い理由は、技術の急速な進歩により、常に学習し続けなければならないプレッシャーがあり、「自分の知識は十分ではない」という感覚を生み出しやすいことです。
インポスター症候群に陥ると、「失敗すると無能さが露呈してしまう」という恐怖から、新しいプロジェクトや技術への挑戦を躊躇し、成長の機会を逸してしまうという悪循環に陥ります。
承認欲求と自己効力感の低下
エンジニアの「しんどさ」の深層には、承認欲求の不充足と自己効力感の低下という心理的な問題があります。
技術的な成果は目に見えにくく、システムの安定稼働やパフォーマンス改善といった重要な貢献が、営業成績のような明確な数値として表れません。
技術の急速な変化により、せっかく習得した技術が短期間で陳腐化してしまうため、「自分の能力は時代遅れになってしまった」という感覚を抱きやすくなります。
これらの心理的問題が組み合わさることで、客観的には十分な能力を持っているエンジニアでも、「自分は価値のない存在だ」という思考のループに陥り、深刻な「しんどさ」を感じることになるのです。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
5. しんどいと感じるエンジニアが現職で改善できる6つの対策
現在の職場環境を改善するための具体的な方法を、実践しやすい順序で解説します。
【STEP 1】一人で抱えず、状況を客観的に伝える
「しんどさ」を一人で抱え込まず、適切に相談することは、問題解決の第一歩です。
相談を成功させるためには、事前の準備が重要です。自分が抱えている問題を具体的に整理し、問題の影響範囲を分析しましょう。「なんとなく辛い」ではなく、「連続3週間、毎日2時間以上の残業が続いている」といった具体的な状況を明確にします。
非エンジニアの上司に相談する際は、技術的な詳細よりも、ビジネスへの影響を中心に説明することが重要です。
「デプロイ作業が複雑で」ではなく、「システム更新に予想以上の時間がかかり、本来の開発業務に支障が出ている」というように、ビジネス的な観点から問題を説明しましょう。
また、問題だけでなく解決策も併せて提案することで、建設的な議論を促進できます。
【STEP 2】時間的・精神的な余裕を生み出す
時間的な余裕の不足は、エンジニアの「しんどさ」の大きな要因です。
エンジニアにとって最も効果的な効率化手法は、反復作業の自動化です。システム監視、ログ分析、定期バックアップなど、日常的に発生する作業をスクリプト化することで、大幅な時間短縮が実現できます。
自動化対象の例
- デプロイメント作業とテストの実行
- ログファイルの整理と分析
- 定期的なシステムチェックとバックアップ
効率化の基本は、適切なタスク管理です。緊急度と重要度を基準にタスクを分類し、
- 重要かつ緊急
- 重要だが緊急でない
- 緊急だが重要でない
- 緊急でも重要でもない
の4象限に整理しましょう。
特に「重要だが緊急でない」タスクに時間を割くことで、将来的な問題を予防できます。
【STEP 3】学習プランの見直しとコミュニティの活用
技術学習のプレッシャーを軽減するためには、効率的な学習戦略の構築が重要です。
多くのエンジニアが陥りがちな罠が、「学習のための学習」です。技術書を最初から最後まで読破することにこだわるのではなく、実際の業務で必要になったタイミングで、必要な部分だけを効率的に学習する「ジャストインタイム学習」を実践しましょう。
効率的な技術キャッチアップの流れ
- 概要把握(15分程度)で公式ドキュメントや信頼できる記事で全体像を理解
- ハンズオン(1時間程度)で簡単なチュートリアルを実際に動かしてみる
- 実務適用の検討(30分程度)で自分の業務にどう活用できるかを考える
- 深掘り学習は実際に使う場面で詳細を学ぶ
技術コミュニティは、学習効率を大幅に向上させる貴重なリソースです。Qiita、GitHub Trendingなどで最新技術情報を効率的に収集し、Stack OverflowやteratailなどのQ&Aサイトで技術的な疑問を素早く解決できます。
【STEP 4】小さな成功体験を重ね、自信を育む
インポスター症候群や自己効力感の低下に対抗するためには、小さな成功体験を意識的に積み重ねることが重要です。
日々の小さな成功を記録する習慣を身につけましょう。「バグを1つ修正した」「新しいライブラリを使えるようになった」「チームメンバーから感謝された」といった些細な出来事でも、積み重ねることで自信につながります。
週次で「今週できるようになったこと」を3つずつ書き出したり、技術ブログやQiitaに学んだことを投稿したり、GitHubのコミット履歴を振り返って成長を実感したり、同僚からもらったポジティブなフィードバックを保存するなど、自分なりの記録方法を見つけることが大切です。
【STEP 5】働き方改善を交渉してみる
現職での働き方を改善するためには、適切な交渉術を身につけることが重要です。
感情論ではなく、客観的なデータに基づいて交渉することで、説得力を高められます。「自分だけが得をする」のではなく、会社にとってもメリットがある提案を心がけましょう。
「残業を減らしたい」ではなく、「業務効率化により、より付加価値の高い業務に集中できるようになります」といった表現で、双方にメリットがあることを強調します。
【STEP 6】セルフケアを実践し、心身の健康を守る
エンジニアの「しんどさ」に対処するためには、積極的なメンタルヘルスケアが不可欠です。自分固有のストレス要因を特定し、それぞれに対する対処法を用意しておきましょう。
短時間で効果的にリフレッシュできる技術を身につけ、仕事とプライベートの境界を明確にし、意識的にリラックスできる時間を確保しましょう。
セルフケアだけでは限界がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。多くの企業でEAP(従業員支援プログラム)が提供されており、カウンセリングサービスを利用することができます。
6. しんどいエンジニアが転職を検討すべき判断基準と成功のポイント
転職という大きな決断をする前に、現職改善・休職・転職の3つの選択肢を客観的に検討することが重要です。
現職改善 vs 休職 vs 転職:適切な選択肢の判断
転職を検討する際は、現職で技術的・キャリア的な成長が見込めるか、労働環境の改善可能性、正当な評価の期待度、ライフプランとの整合性を評価しましょう。
休職を優先すべきケース
睡眠障害や食欲不振が2週間以上続いている、仕事への集中力が著しく低下している、職場のことを考えると強い不安や憂鬱感がある場合は、転職よりもまず休職を検討すべきです。
厚生労働省のガイドラインでは、メンタルヘルス不調により業務に支障をきたしている場合、適切な休養と治療により職場復帰が可能であることが示されています。
休職制度は多くの企業の就業規則に定められており、人事部門や上司への相談、産業医面談から始めます。休職中は傷病手当金として健康保険から標準報酬日額の3分の2が最大1年6ヶ月間支給される可能性があります。
参考:厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」 「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
転職を控えるべきケース
- 入社から1年未満で基本的なスキルが身についていない
- 一時的な繁忙期で判断が感情的になっている
- 転職理由が明確でない
- メンタルヘルス不調の症状が顕著に現れている
転職で解決できること・できないこと
転職で解決できる問題 vs 解決できない問題
- 解決できる:労働環境の改善、技術的成長機会の拡大、年収・待遇の向上、キャリアパスの変更
- 解決できない:根本的な性格特性(完璧主義、インポスター症候群など)、業界全体の構造的問題、対人関係やコミュニケーションの根本的課題
特に注意が必要なのは、メンタルヘルス不調が原因の場合です。根本的な原因が個人の心理的特性や業界全体の問題にある場合、転職だけでは解決されない可能性があります。
転職成功のための準備と戦略
転職を成功させるためには、スキルの棚卸し、市場価値の把握、転職理由の明確化、キャリアプランの設定が必要です。応募書類では職務経歴書の完成とポートフォリオの整備、面接対策では転職理由の練習と技術的質問への対応準備が重要です。
転職成功者が実践している重要なポイント
市場動向を考慮したタイミングの選択、複数企業への並行応募、継続的な技術学習とアウトプットです。重要なのは、転職を「現状からの逃避」ではなく「キャリア目標達成のための戦略的行動」として位置づけることです。
休職経験がある場合は、面接で休職理由、治療内容、現在の健康状態、再発防止策を前向きに説明できるよう準備しておきましょう。
7. AI時代にしんどくならないエンジニアになる方法
AI時代を生き抜くエンジニアのキャリア戦略
AIと共存し、価値を高める3つの必須スキル。
AI技術の発展が加速する中、エンジニアとして持続可能なキャリアを築くための戦略を解説します。
AI脅威論を客観視:本当のリスクと機会を理解する
「AIがエンジニアの仕事を奪う」という議論が活発化していますが、まず冷静に現状を把握することが重要です。
「4年以内に業務の半分以上がAIに代替される」と予測するエンジニアが増えている一方で、実際のAI開発現場では人間のエンジニアがより重要な役割を担うようになっています。
完全自律型AIエージェント「Devin」を開発した米Cognition AI CEOのスコット・ウー氏は、「エンジニア不要論」に真っ向から異議を唱え、「AIによって10倍の数のソフトウェアを生み出せる今こそ、エンジニアがより重要な存在になる」と述べています。
総務省の調査によると、日本のAI市場は2019年の400億円から2025年には1200億円以上へと3倍の成長が予測されており、AI人材の需要は企業の需要に対して明らかに不足している状況です。
AIと共存するための必須スキル3選
AI時代のエンジニアに求められるスキルは、従来の技術スキルとは異なる側面があります。
課題発見力とビジネス実装力
今後は上流工程でのバリュー発揮がエンジニアにとって重要なポイントになると分析されており、顧客のビジネスニーズを的確にヒアリングし、それを技術仕様に落とし込む能力がますます重要になります。
AIが自動化できるのは定型的な作業であり、人間らしい柔軟なコミュニケーションによる課題発見と解決策の提案は、依然として人間の領域です。
AI技術の理解と活用スキル
「AIを恐れるのではなく、活用する」姿勢が重要です。GitHub Copilotのようなコード生成AIを効果的に使いこなし、開発効率を向上させることができるエンジニアと、AIを使わずに従来の方法に固執するエンジニアとの間には、生産性において大きな差が生まれています。
実際に6〜7割以上のエンジニアがGitHub Copilotを活用し、推薦されたコードの3〜4割が採択されている状況で、2割前後の生産性改善を実現している企業もあります。
問題発見・解決・仕組み化の総合能力
AIが既存の問題を効率的に処理できる一方で、「そもそも何が問題なのか」を発見し、根本的な解決策を考案し、同様の問題が再発しないような仕組みを構築する能力は、人間独自の価値として残り続けます。
この能力は単なる技術力ではなく、ビジネス理解、創造性、論理的思考力を組み合わせた総合力です。
長期的なキャリア戦略:専門性と汎用性のバランス
AI時代のエンジニアキャリアでは、専門性と汎用性のバランスが重要になります。まず一つの技術を深く極めることが基盤として不可欠です。深い専門性は簡単には代替できない価値を生み出します。しかし、AI時代では単一技術への特化だけでは限界があります。
複数の技術領域への理解を広げる
フルスタック的な知識を持ち、フロントエンドからバックエンド、インフラまで幅広く対応できるエンジニアの需要が高まっています。AIによって個々の作業は効率化されますが、システム全体を設計し、各技術要素を適切に組み合わせる能力は、より価値の高いスキルとなります。
技術以外の領域への理解
金融、医療、教育など、特定の業界に深い知識を持つエンジニアは、AI時代においても強い競争力を維持できます。AIは汎用的な解決策を提供できますが、業界特有の課題や規制への対応には、人間の専門知識が不可欠です。
継続的な学習習慣の確立も欠かせませんが、従来の「とにかく新技術を覚える」アプローチではなく、「実際の業務で必要になったタイミングで効率的に学習する」ジャストインタイム学習が重要になります。
8. まとめ:エンジニアのしんどさを解決する次の一歩へ
エンジニアの「しんどさ」は決して甘えではなく、業界全体が抱える構造的な課題です。
重要なのは、その現状を受け入れた上で、自分に合った解決策を見つけることです。
現職での改善から転職、そしてAI時代への対応まで、段階的なアプローチで着実に前進していきましょう。
今日から実践できる小さな一歩が、理想的なエンジニアキャリアの出発点となります。