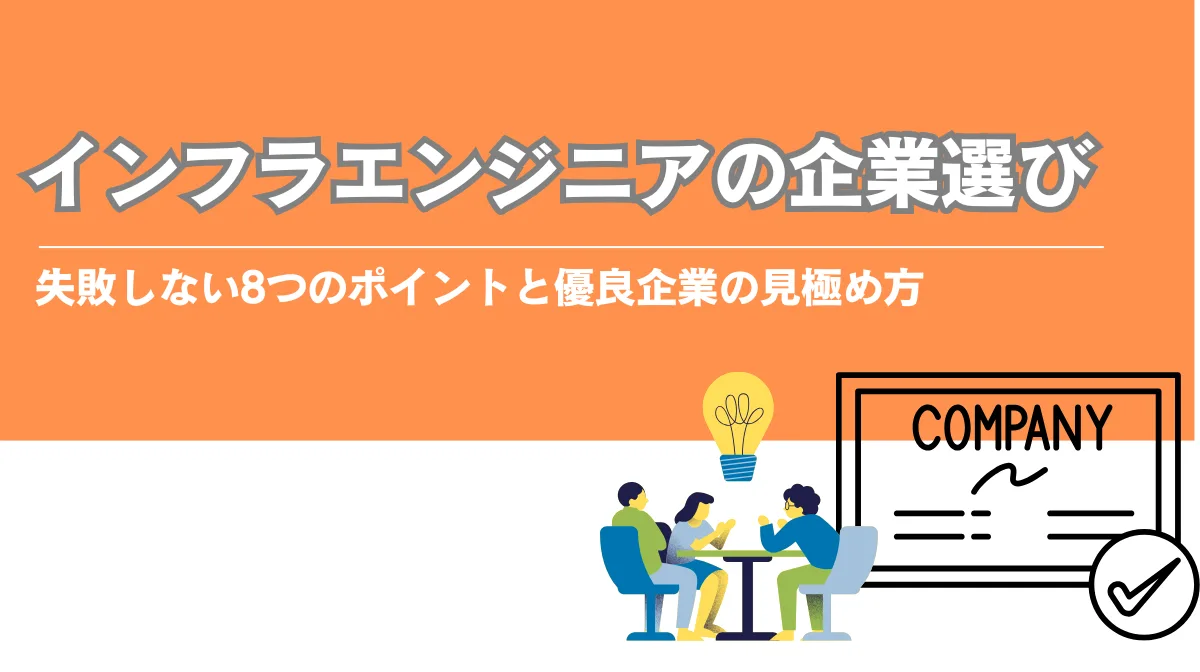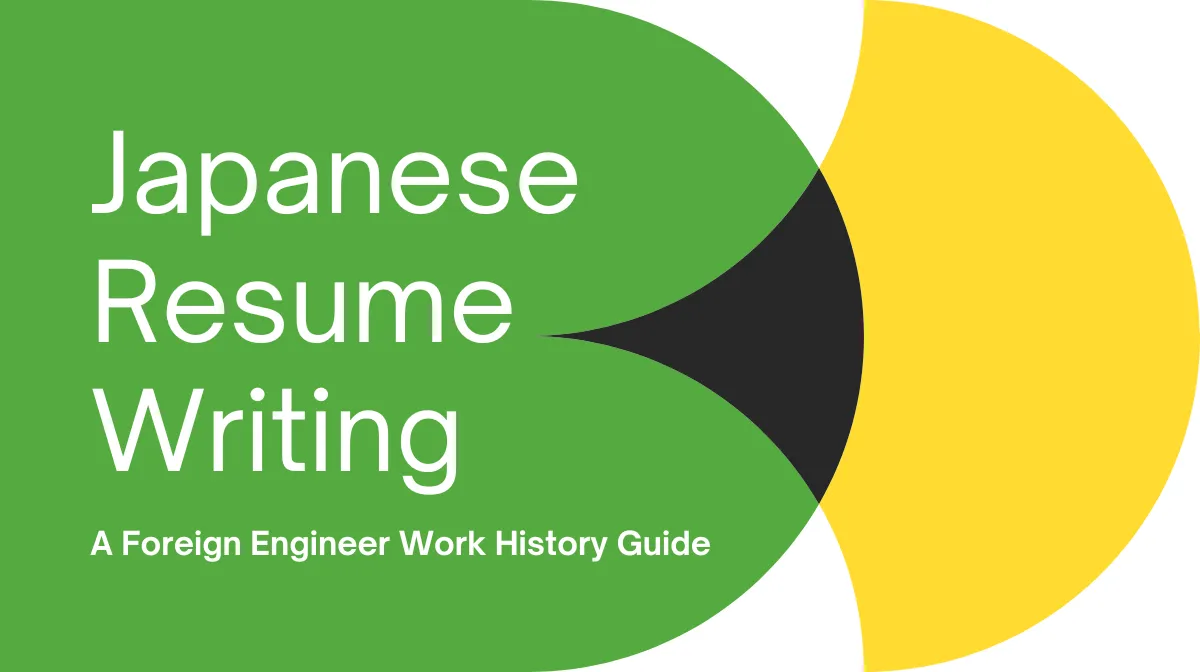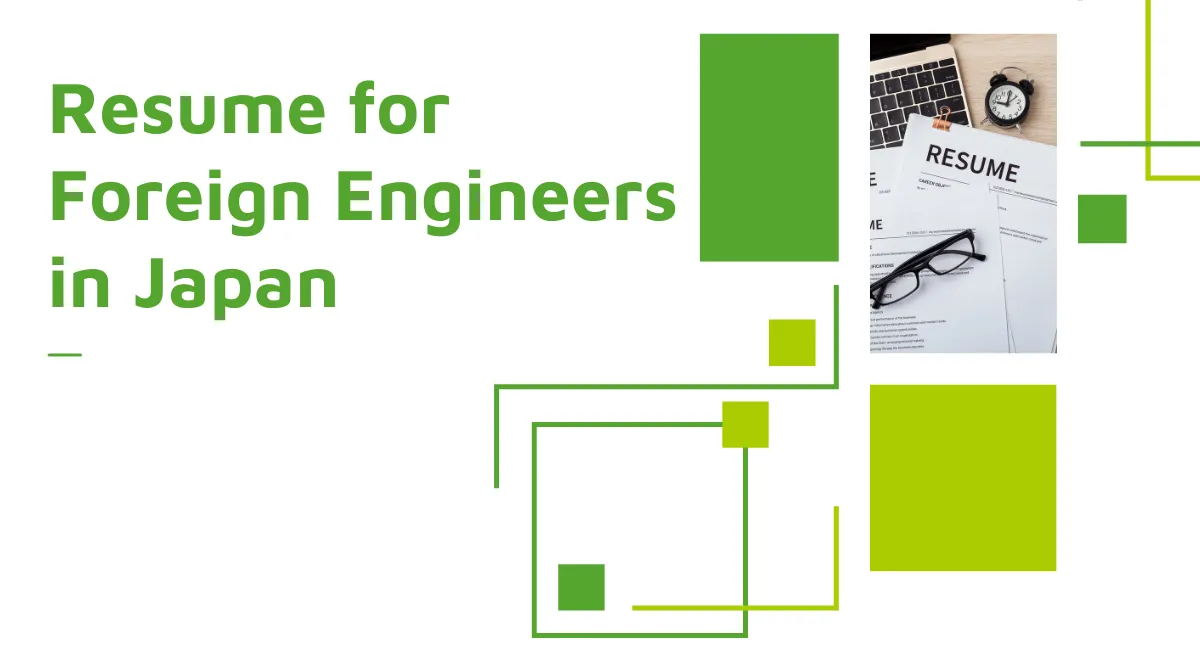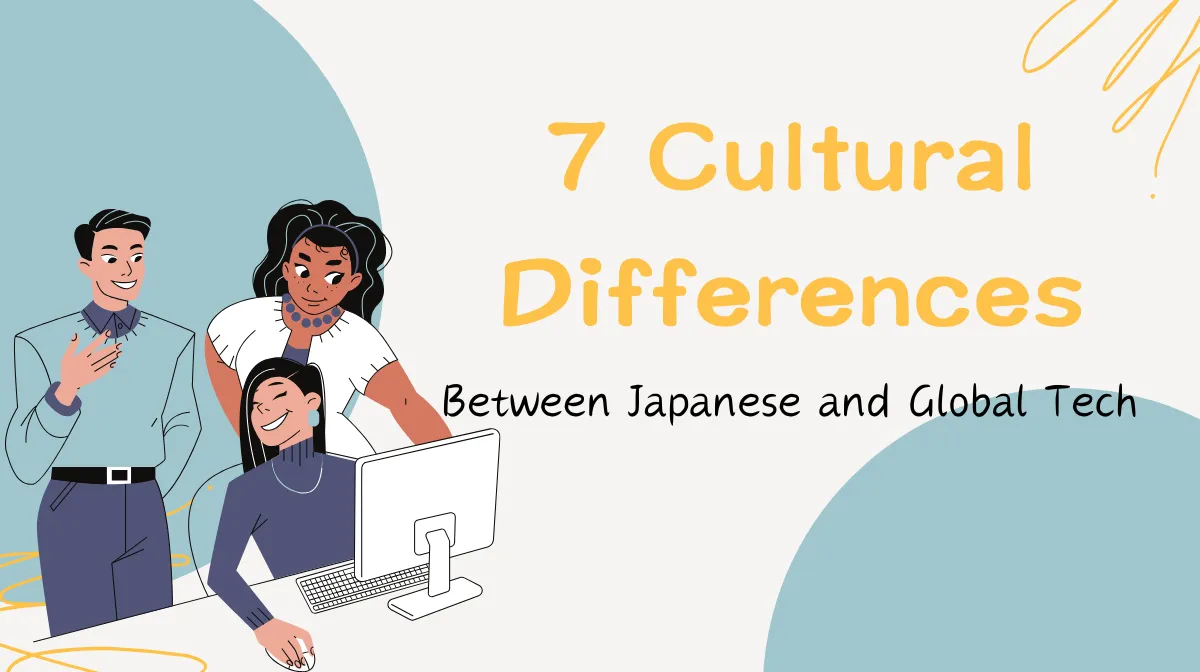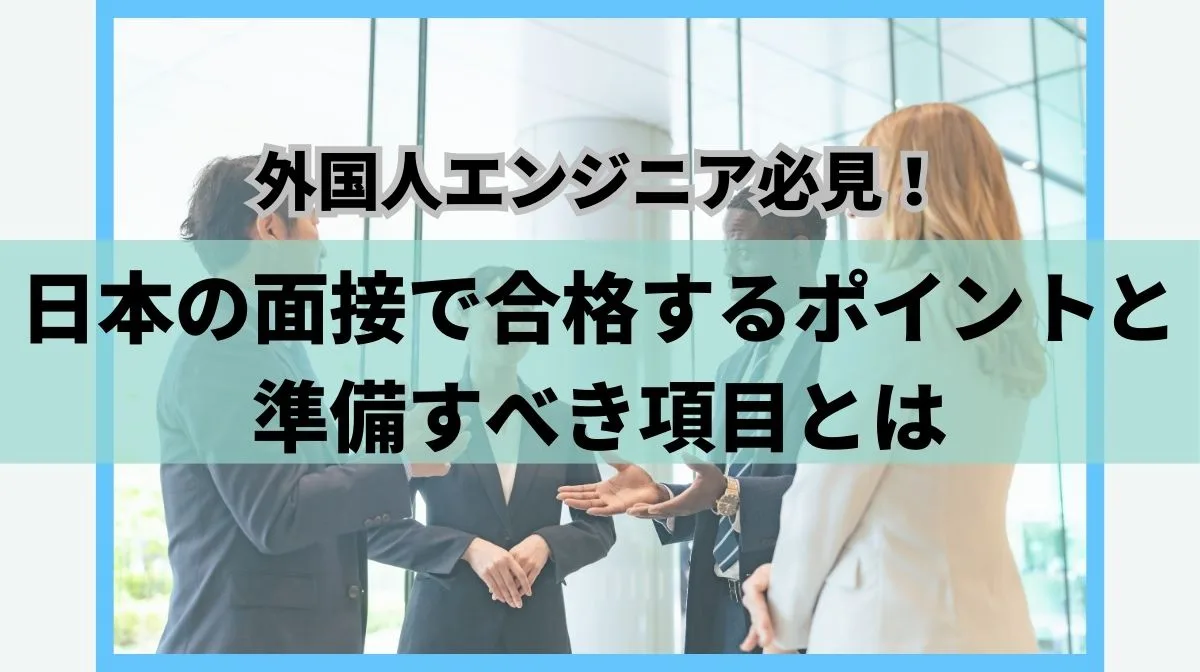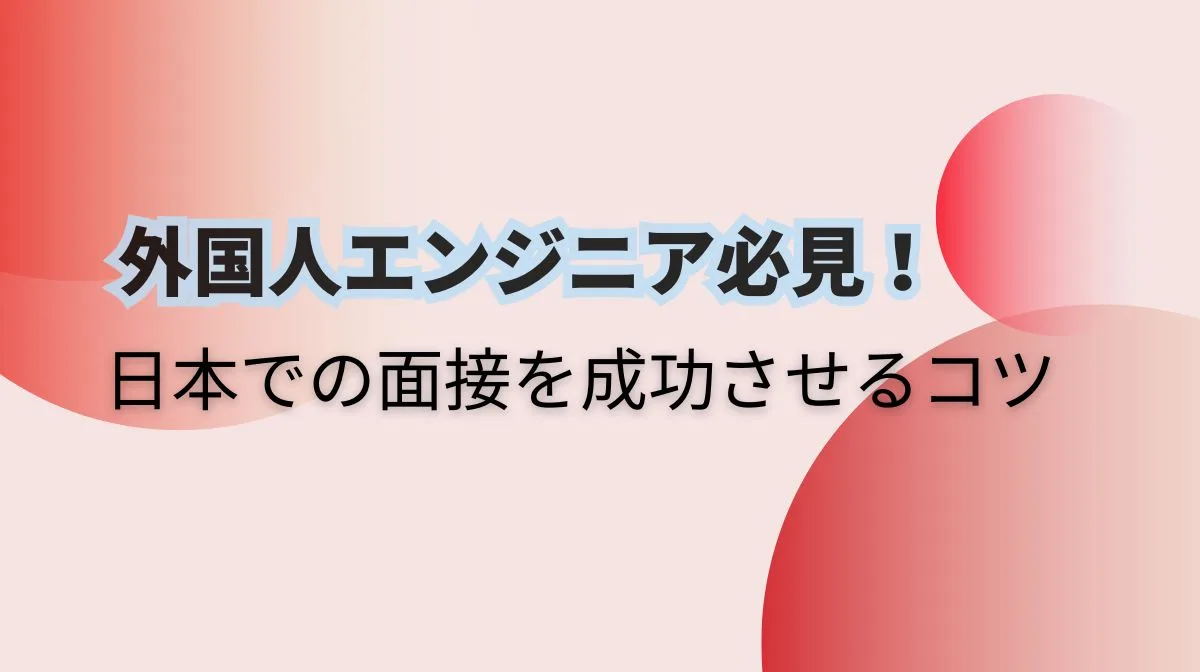インフラエンジニアとして転職を考える際、企業選びは今後のキャリアを大きく左右する重要な決断となります。
しかし、実際には転職後に「給与や昇進についての問題」で不満を感じるITエンジニアが多く、20代ITエンジニアの約8割が5年以内に離職を検討しているという調査結果も出ています。
この記事では、こうした失敗を防ぐために、インフラエンジニアが企業選びで確認すべき8つのポイントを詳しく解説します。
未経験者から転職検討中の経験者まで、優良企業を見極めるための具体的な基準を提示していきます。
※この記事の英語版をお読みになりたい方は、こちらになります。(Read this article in English, please click here!)
- インフラエンジニアが企業選びで失敗する原因とリスクについて
- 優良企業を見極めるための8つの具体的なチェックポイントについて
- 未経験者が特に注意すべき企業選びのポイントと効率的な情報収集方法について
1. インフラエンジニアとは?企業選びの前に知るべき基礎知識

企業選びを始める前に、まずはインフラエンジニアの仕事内容や年収、将来性といった基礎知識を正しく理解しておくことが重要です。
自分が目指す職種の全体像を把握することで、より適切な企業選びの判断ができるようになります。
インフラエンジニアの定義と主な役割
インフラエンジニアとは、Weblio辞書によると「企業の情報システムを構築するITエンジニアのカテゴリの一つで、主にIT基盤(インフラストラクチャー)の構築を担当する職種」と定義されています。
具体的には、ハードウェア、仮想化、OS、ネットワーク、ミドルウェア、セキュリティといった、システムを支える基盤全体を担当する技術者を指します。
インフラエンジニアが構築したシステム基盤に、アプリケーションエンジニアが開発したソフトウェアを導入することで、業務システムが完成します。
近年では、クラウドコンピューティングやデータセンターの運用管理も重要な職務範囲となっています。
インフラエンジニアは、担当する領域によって大きく3つに分類されます。
サーバーエンジニアの役割
サーバーエンジニアは、Webサーバーやデータベースサーバーなど、各種サーバーの設計・構築・運用を担当します。
サーバーのスペック選定から、OSのインストール、ミドルウェアの設定、パフォーマンスチューニングまで幅広い業務を行います。
物理サーバーだけでなく、仮想化技術を活用した仮想サーバーの管理も重要な役割となっています。
ネットワークエンジニアの役割
ネットワークエンジニアは、企業内のネットワーク環境の設計・構築・運用を担当します。
ルーターやスイッチといったネットワーク機器の設定、LANやWANの構築、ネットワークセキュリティの実装などを行います。
安定した通信環境を提供し、システム全体のパフォーマンスを最適化することが求められます。
クラウドエンジニアの役割
クラウドエンジニアは、AWS、Azure、GCPといったクラウドプラットフォーム上でのインフラ設計・構築・運用を担当します。
オンプレミス環境からクラウド環境への移行支援や、クラウドサービスを活用したコスト最適化、スケーラビリティの確保などが主な業務です。
近年のDX推進により、最も需要が高まっている分野の一つとなっています。
インフラエンジニアの平均年収(年代別データ)
インフラエンジニアの平均年収は、厚生労働省が提供する職業情報サイト「jobtag」によると684.9万円です。
国税庁の調査による日本の平均年収530万円(例:令和4年分 民間給与実態統計調査)と比較すると、約150万円以上高い水準にあり、高収入が期待できる職種といえます。
年代別に見ると、以下のような年収推移となっています。
20代の平均年収
20~24歳で373万円、25~29歳で511.69万円となっています。未経験から入社した場合でも、スキルを積むことで20代後半には500万円台の年収を目指すことができます。
30代の平均年収
30~34歳で627.71万円、35~39歳で747.01万円と、年代が上がるにつれて着実に年収が上昇していきます。30代では専門性を高めることで、700万円台の年収も十分に射程圏内に入ります。
40代以降の年収推移
40~44歳で698.97万円、45~49歳で784.19万円、50~54歳で793.39万円と、40代以降も安定して高収入を維持できます。55~59歳では848.21万円とピークを迎え、技術力やマネジメント経験を活かして高い報酬を得ることが可能です。
インフラエンジニアの将来性と市場需要
インフラエンジニアの将来性は極めて高く、今後も継続的に需要が拡大していくと予測されています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する「DX白書2023」によると、DX推進における課題として「DX人材の不足」を挙げる企業が従業員21人以上の企業で41.8%、「IT人材の不足」が33.4%に達しており、深刻な人材不足が続いています。
クラウド移行による需要増加
企業のクラウド移行が加速する中、AWSやAzure、GCPといったクラウドプラットフォームの設計・構築・運用ができるクラウドエンジニアの需要が急増しています。
従来のオンプレミス環境の知識に加え、クラウド技術を習得することで、市場価値を大きく高めることができます。
セキュリティ強化ニーズの高まり
サイバー攻撃の高度化や情報漏洩リスクの増大により、セキュリティ対策への投資が増加しています。
ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、ゼロトラストアーキテクチャなど、セキュリティに関する専門知識を持つインフラエンジニアは、今後さらに重要な役割を担うことになります。
これらのデータから、インフラエンジニアは技術の進化とともに需要が高まり続ける、将来性の高い職種であることが分かります。
企業選びにおいては、こうした市場動向を踏まえ、最新技術を学べる環境があるかどうかを重視することが重要です。
出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」
2. インフラエンジニアの企業選びで失敗するとどうなるか

企業選びの失敗は、単に「転職に失敗した」というだけでは済まされません。キャリア全体に長期的な悪影響を及ぼし、取り返しのつかない時間を失うリスクがあります。
ここでは、実際のデータをもとに、企業選びで失敗した場合にどのような問題が起こるのかを見ていきます。
転職後に不満を感じるITエンジニアの実態
マンパワーグループ株式会社が実施した調査によると、転職後に不満を感じる理由として「給与や昇進についての問題」が最も多く挙げられています。
さらに深刻なのは、現在の会社で「5年以上」働き続けたいと考える20代ITエンジニアがわずか2割弱しかいないという事実です。
つまり、20代ITエンジニアの約8割が、入社後5年以内に離職を検討しているということになります。
この背景には、企業選びの段階で十分な情報収集や判断ができていないことが大きな要因として考えられます。入社前のイメージと入社後の現実にギャップがあり、早期離職につながるケースが後を絶ちません。
出典:マンパワーグループ株式会社「いまの会社で「5年以上」働き続けたい20代ITエンジニアはわずか2割弱」
スキルアップできない環境に陥るリスク
企業選びに失敗すると、最も深刻な問題となるのがスキルアップできない環境に長期間身を置くことになるリスクです。
下請け案件ばかりを担当させられ、単純作業や監視業務のみに従事することになると、技術力が身につかず、市場価値が上がらないままキャリアの時間だけが過ぎていきます。
20代という貴重な成長期間を、学びのない環境で過ごすことは、その後のキャリアに致命的な影響を与えます。
長時間残業とワークライフバランスの崩壊
教育体制が整っていない企業では、プロジェクトの進行管理が杜撰で、慢性的な長時間残業が発生するケースが多く見られます。
月間残業時間が50時間、80時間と常態化すると、プライベートの時間が奪われるだけでなく、自己学習の時間も確保できなくなります。心身の健康を損ない、バーンアウトに至るケースも少なくありません。
キャリアの選択肢が狭まる
スキルが身につかない環境で数年を過ごすと、次の転職時に提示できる実績やスキルセットが限定的になり、キャリアの選択肢が大幅に狭まります。
市場価値の低い状態が固定化され、年収アップの機会を逃し続けることになります。
特に30代以降は、専門性やマネジメント経験が求められるため、20代でのスキル蓄積が極めて重要です。
ブラック企業に共通する3つの特徴
インフラエンジニアの転職市場において、避けるべきブラック企業には明確な共通点が存在します。以下の3つの特徴を理解しておくことで、企業選びの失敗を未然に防ぐことができます。
下請け案件ばかりで技術力が身につかない
元請け企業から仕事を受注する二次請け、三次請けの企業では、上流工程(要件定義や設計)に携わる機会がほとんどなく、構築や運用保守といった下流工程のみを担当することになります。
指示された作業をこなすだけの日々が続き、システム全体を理解する力や、自ら設計を行うスキルが一切身につきません。
こうした環境では、数年経っても市場価値が上がらず、転職市場で評価されにくい状態が続きます。
教育制度がなく放置される
未経験者を採用しながら、実際には教育体制が全く整っていない企業が存在します。
入社後にOJTもメンター制度もなく、いきなり現場に配属されて放置される状態では、何を学べばいいのか分からないまま時間だけが過ぎていきます。
質問できる環境もなく、自力で解決するしかない状況は、特に未経験者にとって大きなストレスとなり、早期離職の原因となります。
評価制度が不透明で給与が上がらない
評価基準が明確でない企業では、どれだけ努力しても正当な評価を受けられず、給与が上がらない状況が続きます。
昇給の仕組みが不透明で、年功序列でもなく、成果主義でもない曖昧な評価制度では、モチベーションの維持が困難です。
入社時の給与から数年間ほとんど変わらず、同業他社と比較して大きく年収が低い状態が固定化されることもあります。
これらのブラック企業の特徴を事前に知っておくことで、企業選びの段階で警戒すべきポイントが明確になります。次章では、こうしたブラック企業を避け、優良企業を見極めるための具体的なチェックポイントを解説していきます。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
3. インフラエンジニアの企業選びで確認すべき8つのポイント
ブラック企業を避け、優良企業を見極めるためには、客観的かつ具体的な判断基準が必要です。
ここでは、インフラエンジニアが企業選びで必ず確認すべき8つのポイントを、実際の確認方法とともに詳しく解説します。
ポイント①:元請けプロジェクトの比率は70%以上か
企業が受注しているプロジェクトの中で、元請け案件が全体の70%以上を占めているかどうかは、技術力向上の観点から極めて重要な指標です。
元請け企業は、顧客から直接案件を受注するため、要件定義や基本設計といった上流工程に携わる機会が多くなります。
一方、二次請け、三次請けの企業では、詳細設計や構築、運用保守といった下流工程のみを担当することが多く、システム全体を俯瞰する力が身につきにくくなります。
上流工程の経験は、インフラエンジニアとしての市場価値を大きく左右します。
顧客の要望を聞き取り、それを技術的な仕様に落とし込むプロセスを経験することで、技術力だけでなくコミュニケーション能力やビジネス理解力も磨かれます。
企業サイトの実績ページを確認
企業の公式サイトにある「導入実績」や「プロジェクト事例」のページを確認しましょう。
大手企業名が直接のクライアントとして掲載されている場合、元請け案件である可能性が高いです。
また、案件の内容説明に「要件定義から運用まで一貫して担当」といった記述があれば、上流工程に携われる環境である証拠となります。
面接で直接質問する方法
面接の場で、「御社が受注しているプロジェクトの中で、元請け案件と二次請け以降の案件の比率はどのくらいですか?」と直接質問することも有効です。
優良企業であれば、この質問に対して具体的な数値や事例を示して答えてくれます。曖昧な回答しか得られない場合は、注意が必要です。
口コミサイトでの調査
OpenWorkや転職会議といった口コミサイトでは、実際に働いている社員や元社員の生の声を確認できます。
「どのような案件に携われるか」「上流工程の経験ができるか」といった観点でレビューをチェックしましょう。
複数の口コミで下請け案件が多いという指摘があれば、慎重に判断する必要があります。
ポイント②:30代・40代社員の比率は適切か
企業の年齢構成は、その企業の安定性と成長性を判断する重要な指標です。理想的な年齢構成は、30代・40代の中堅層が全体の50%程度を占めている状態です。
この年代層が厚い企業は、若手を指導できるメンターが豊富に存在し、組織としての技術の蓄積もしっかりしている傾向があります。
年齢構成から分かる企業の安定性
逆に、20代ばかりの企業は離職率が高い可能性があります。中堅層が育たずに次々と辞めていくため、若手ばかりが残る構造になっているケースです。
また、50代以上が大半を占める企業は、新しい技術への対応が遅れており、成長性に欠ける可能性があります。30代・40代のバランスが取れた年齢構成こそが、安定して長く働ける環境の証といえます。
確認方法(採用ページ、会社説明会)
企業の採用ページには、社員紹介や組織図が掲載されていることがあります。そこに登場する社員の年齢層を確認しましょう。
また、会社説明会やオフィス見学の機会があれば、実際に働いている社員の年齢層を観察することも有効です。面接時に「御社の年齢構成について教えていただけますか?」と質問するのも一つの方法です。
ポイント③:平均残業時間は月20時間以内か
残業時間の長さは、ワークライフバランスを保ち、継続的に学習できる環境があるかどうかを判断する上で重要な指標です。
月間平均残業時間が20時間以内であれば、プライベートの時間を確保しつつ、自己学習の時間も十分に取れます。
一方、月間残業時間が50時間を超えるような企業では、心身の健康を損なうリスクが高まります。
求人票の残業時間記載をチェック
求人票には平均残業時間が記載されていることが多いです。「月間平均残業時間:15時間」といった具体的な数値が明記されている企業は、労働時間管理がしっかりしている可能性が高いです。
ただし、「繁忙期を除く」といった但し書きがある場合は、実態がどうなのかを面接で確認する必要があります。
面接で具体的な働き方を質問
面接では、「実際の1日の働き方を教えてください」「繁忙期はどのくらいの頻度でどのくらいの残業になりますか?」といった具体的な質問をしましょう。
優良企業であれば、実態を正直に答えてくれます。曖昧な回答しか得られない場合や、話題を逸らそうとする場合は警戒が必要です。
口コミサイトの残業実態
口コミサイトでは、「残業時間」や「ワークライフバランス」に関する評価を確認できます。
複数の口コミで「残業が多い」「帰れない」といった指摘が見られる場合は、実態として長時間労働が常態化している可能性が高いです。
ポイント④:教育・研修制度は充実しているか
特に未経験者や経験の浅いエンジニアにとって、教育・研修制度の充実度は企業選びの最重要ポイントです。
体系的な研修プログラムがあり、メンター制度が整備されている企業であれば、安心してスキルを積み上げていくことができます。
OJT・メンター制度の有無
入社後に先輩社員がマンツーマンで指導してくれるメンター制度があるかどうかを確認しましょう。
OJT(On-the-Job Training)だけでなく、定期的な1on1ミーティングやフィードバックの機会があるかも重要です。
メンター制度が明文化されている企業は、人材育成に真剣に取り組んでいる証拠といえます。
資格取得支援制度(CCNA、LPIC等)
CCNA、LPIC、AWS認定資格といった業界標準の資格取得を支援する制度があるかを確認しましょう。
受験料の全額負担や、合格時の報奨金制度がある企業は、社員のスキルアップを積極的にサポートしている姿勢が見えます。
資格取得のための学習時間を業務時間として認めてくれる企業もあります。
社内勉強会・外部研修の機会
定期的に社内勉強会が開催されているか、外部のセミナーや研修への参加を推奨・支援しているかも重要なポイントです。
技術の最新トレンドをキャッチアップできる環境があることは、市場価値を高め続けるために不可欠です。
研修制度の実態を見極める質問例
面接では、「入社後の研修プログラムは具体的にどのような内容ですか?」「メンター制度はどのように運用されていますか?」「資格取得支援はどのような制度がありますか?」といった具体的な質問をしましょう。
実態が伴っている企業であれば、詳細なカリキュラムや実績を示して答えてくれます。
ポイント⑤:給与・評価制度は明確か
給与や評価の基準が不透明な企業では、どれだけ成果を上げても正当な報酬を得られず、モチベーションの低下につながります。
評価制度が明文化され、昇給・賞与の仕組みが明確な企業を選ぶことが重要です。
評価基準の開示状況
評価項目やランク、それに応じた報酬体系が社内で明確に開示されているかを確認しましょう。
「スキルマップ」や「等級制度」といった形で評価基準が可視化されている企業は、透明性の高い人事制度を運用しています。
面接時に「評価制度について教えてください」と質問し、具体的な説明が得られるかを確認しましょう。
昇給・賞与の仕組み
年に何回昇給のタイミングがあるのか、賞与は年何回で何ヶ月分が支給されるのかといった具体的な情報を確認します。
また、昇給額の目安や実績も聞いておくと、将来の年収イメージを持ちやすくなります。「入社3年目で年収はどのくらいになりますか?」といった質問も有効です。
インセンティブ制度の有無
プロジェクトの成功や資格取得、技術的な貢献に対してインセンティブが支給される制度があるかも確認しましょう。
成果に応じた報酬が得られる仕組みがあれば、モチベーション高く働き続けることができます。
ポイント⑥:社員の定着率は高いか(離職率は低いか)
優良企業かどうかを見極める一つの指標として、中途採用で入社したインフラエンジニアの定着率が挙げられます。
経験者が増えているということは、その企業が魅力的な環境を提供している証拠です。
新卒3年以内離職率をチェック
企業の採用ページや会社説明会の資料には、新卒3年以内の離職率が公開されていることがあります。
この数値が10%以下であれば、非常に優良な環境といえます。20%を超える場合は、何らかの問題を抱えている可能性が高いです。
中途採用者の定着率
中途採用で入社した社員がどのくらいの期間在籍しているかも重要です。
面接時に「中途入社の方の平均勤続年数はどのくらいですか?」と質問してみましょう。定着率が高い企業は、働きやすい環境が整っている証拠です。
ポイント⑦:福利厚生は充実しているか
福利厚生の充実度は、企業が社員を大切にしているかどうかの指標となります。特に長期的に働くことを考える場合、福利厚生の内容は重要な判断材料です。
社会保険の完備状況
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つがしっかり完備されているかを確認します。
これらは法律で義務付けられている基本的な社会保険ですが、中には加入していない企業も存在するため、必ず確認しましょう。
住宅手当・家族手当
住宅手当や家族手当といった生活支援の手当があるかも確認しましょう。
住宅手当が月2~3万円支給されるだけでも、年収換算で24~36万円の違いになります。家族手当も、将来的なライフプランを考える上で重要な要素です。
リモートワーク制度
近年では、リモートワーク(在宅勤務)制度の有無も重要な福利厚生の一つです。
週に何日リモートワークが可能か、どのような条件で利用できるかを確認しましょう。柔軟な働き方ができる環境は、ワークライフバランスの向上につながります。
退職金制度
退職金制度や企業年金制度があるかも、長期的なキャリアを考える上で重要です。退職金の有無は、老後の生活設計にも大きく影響します。
ポイント⑧:キャリアパスが明確に示されているか
入社後にどのようなキャリアを歩めるのか、明確なキャリアパスが示されているかを確認しましょう。
将来のビジョンが描ける企業であれば、長期的なモチベーションを維持しながら働くことができます。
技術スペシャリストコース
技術を極めていくスペシャリストとしてのキャリアパスが用意されているかを確認します。
シニアエンジニア、リードエンジニア、アーキテクトといった技術職としての上位職位があり、マネジメントに進まなくても高い報酬とポジションを得られる仕組みがあるかが重要です。
マネジメントコース
チームリーダー、プロジェクトマネージャー、部長といったマネジメント職へのキャリアパスが明確に示されているかも確認しましょう。
どのような経験を積めばマネジメント職に進めるのか、その基準が明確であることが重要です。
社内公募制度・ジョブローテーション
社内で別の部署やプロジェクトに挑戦できる社内公募制度があるか、定期的なジョブローテーションがあるかも確認しましょう。
幅広い経験を積める環境があることは、キャリアの選択肢を広げる上で大きなメリットとなります。
これらの8つのポイントを総合的に確認することで、優良企業とブラック企業を見極めることができます。
全てのポイントを満たす完璧な企業を見つけることは難しいかもしれませんが、少なくとも過半数のポイントをクリアしている企業を選ぶことで、企業選びの失敗を大きく減らすことができるでしょう。
4. 未経験者がインフラエンジニアの企業選びで特に注意すべきこと
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、企業選びにおいてさらに慎重な判断が求められます。
「未経験歓迎」という言葉だけに惹かれて入社すると、教育体制が整っていない環境で放置され、結果的にスキルが身につかないまま時間だけが過ぎてしまうリスクがあります。
「未経験歓迎」企業の見極め方
「未経験歓迎」と謳っている企業は多数存在しますが、本当に未経験者を育てる意思と体制がある企業とそうでない企業を見極めることが極めて重要です。
研修期間の長さと内容
本気で未経験者を育てる企業は、最低でも1~3ヶ月の研修期間を設けています。
研修内容も、基礎的なIT知識から始まり、LinuxやネットワークのHands-on実習、実際の機器を使った演習など、体系的なカリキュラムが組まれています。
面接時に「研修プログラムの具体的な内容と期間を教えてください」と質問し、明確なカリキュラムが提示されるかを確認しましょう。
メンター制度の実態
メンター制度があると謳っていても、実態が伴っていない企業も存在します。
「メンターとはどのくらいの頻度でコミュニケーションを取るのですか?」「メンターはどのような経験を持つ方が担当するのですか?」といった質問で、制度の実効性を確認しましょう。
未経験者の配属先プロジェクト
未経験者が最初に配属されるプロジェクトの内容も重要です。
学びの多い案件に配属されるのか、単純作業ばかりの案件に配属されるのかで、その後の成長曲線が大きく変わります。
「未経験者は最初にどのような案件を担当することが多いですか?」と質問してみましょう。
SES企業を選ぶ場合の注意点
SES(System Engineering Service)企業は、エンジニアを顧客企業に常駐させて技術サービスを提供するビジネスモデルです。
SES企業にはメリットとデメリットがあるため、慎重に見極める必要があります。
自社内開発案件の有無
優良なSES企業は、客先常駐案件だけでなく、自社内で開発するプロジェクトも保有しています。
自社内案件があることで、チームワークを学べたり、プロジェクト全体の流れを経験できたりするメリットがあります。
「自社内での開発案件はどのくらいありますか?」と質問してみましょう。
キャリアサポート体制
SES企業では、エンジニアが孤立しがちです。
優良なSES企業は、定期的な面談やキャリア相談の機会を設け、エンジニアの成長をサポートする体制を整えています。
「常駐先で困ったことがあった場合、どのようなサポートがありますか?」といった質問で確認しましょう。
スキルアップ支援策
資格取得支援、社内勉強会の開催、技術書購入補助など、常駐中でもスキルアップできる支援策があるかを確認します。
優良なSES企業は、エンジニアの市場価値を高めることが自社の競争力につながると理解しているため、積極的にスキルアップを支援します。
入社前に取得すべき資格
未経験者が企業選びを有利に進めるためには、入社前に基礎的な資格を取得しておくことが効果的です。
資格は自己学習の証明となり、企業側に「学ぶ意欲がある」ことをアピールできます。
CCNA(ネットワーク)
Cisco技術者認定であるCCNAは、ネットワークエンジニアを目指す上で最も基本的かつ重要な資格です。
ネットワークの基礎知識を体系的に学べるため、未経験者が最初に取得すべき資格として広く認知されています。
LPIC(Linux)
Linux技術者認定であるLPIC-1は、サーバーエンジニアを目指す上で有用な資格です。
LinuxはIT基盤の中核を担うOSであり、基礎知識を持っていることは大きなアドバンテージになります。
AWS認定資格(クラウド)
クラウドエンジニアを目指す場合は、AWS認定クラウドプラクティショナーの取得がおすすめです。
クラウドの基礎知識を証明でき、クラウド案件の多い企業への転職に有利になります。
これらの資格を1~2つ取得してから転職活動を行うことで、未経験でも書類選考の通過率が大きく向上します。
■日本でエンジニアとしてキャリアアップしたい方へ
海外エンジニア転職支援サービス『 Bloomtech Career 』にご相談ください。「英語OK」「ビザサポートあり」「高年収企業」など、外国人エンジニア向けの求人を多数掲載。専任のキャリアアドバイザーが、あなたのスキル・希望に合った最適な日本企業をご紹介します。
▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!
Bloomtech Careerに無料相談してみる
5. インフラエンジニアの優良企業を効率的に探す方法

優良企業を見つけるためには、複数の情報源を活用し、多角的に企業を評価することが重要です。
一つの情報だけを鵜呑みにせず、複数の視点から企業を見極めましょう。
企業の情報収集に使うべきツール
企業の公式サイト・採用ページ
企業の公式サイトは最も基本的な情報源です。事業内容、取引先企業、プロジェクト事例、社員インタビューなどから、企業の実態を把握できます。
特に採用ページには、福利厚生や研修制度、キャリアパスなどの詳細情報が掲載されていることが多いです。
転職口コミサイト(OpenWork、転職会議等)
OpenWorkや転職会議といった口コミサイトには、実際に働いている社員や元社員の生の声が掲載されています。
給与、残業時間、社風、教育体制などのリアルな情報を確認できます。ただし、口コミには個人の主観が含まれるため、複数の口コミを総合的に判断することが大切です。
企業の財務情報(上場企業の場合)
上場企業であれば、有価証券報告書や決算短信から財務状況を確認できます。
売上高の推移、営業利益率、自己資本比率などから、企業の安定性や成長性を判断できます。財務が健全な企業は、長期的に安心して働ける可能性が高いです。
転職エージェントの効果的な活用法
転職エージェントを活用することで、個人では入手しにくい情報を得ることができます。
非公開求人へのアクセス
転職エージェントは、一般には公開されていない非公開求人を多数保有しています。優良企業の求人は非公開で募集されることが多いため、エージェントの活用は必須といえます。
企業の内部情報の入手
エージェントは、企業の採用担当者と定期的にコミュニケーションを取っているため、求人票には載っていない内部情報を持っています。
実際の残業時間、離職率、社風、プロジェクトの内容など、踏み込んだ情報を教えてもらえることがあります。
年収交渉のサポート
年収交渉はデリケートな問題ですが、エージェントが間に入ることで、スムーズに交渉を進めることができます。市場価値に基づいた適正な年収を提示してもらえる可能性が高まります。
面接で必ず確認すべき質問リスト
面接は企業を見極める最も重要な機会です。以下の質問を必ず行いましょう。
プロジェクトの種類と比率
「御社が担当しているプロジェクトは、元請け案件と二次請け以降の案件でどのくらいの比率ですか?」「どのような業界のプロジェクトが多いですか?」
平均残業時間と繁忙期の働き方
「平均的な残業時間はどのくらいですか?」「繁忙期はどのくらいの頻度でどのくらいの残業になりますか?」「リモートワークは可能ですか?」
評価制度と昇給実績
「評価制度はどのように運用されていますか?」「昇給は年に何回ありますか?」「入社3年目の平均年収はどのくらいですか?」
研修制度の具体的な内容
「入社後の研修プログラムは具体的にどのような内容ですか?」「メンター制度はどのように運用されていますか?」「資格取得支援制度はありますか?」
これらの質問を通じて、企業の実態を多角的に把握し、自分に合った優良企業を見極めることができます。
6. インフラエンジニアのキャリアパス
インフラエンジニアとして長期的にキャリアを築いていくためには、将来のキャリアパスを描き、計画的にスキルを積み上げていくことが重要です。
インフラエンジニアの3つのキャリアパス
技術スペシャリストとして深化
技術を極めるスペシャリストの道では、特定の技術領域で深い専門性を持つエンジニアを目指します。
セキュリティエンジニア、クラウドアーキテクト、SREといった高度な技術職に進むことで、高い市場価値と報酬を得ることができます。
技術の最先端に常に触れ続け、専門性を深めることが求められます。
マネジメント職への転換
プロジェクトマネージャーやチームリーダーといったマネジメント職を目指す道です。
技術的な知識に加え、プロジェクト管理能力、メンバーの育成能力、コミュニケーション能力が求められます。技術部長やCTOといった経営層を目指すこともできます。
ITコンサルタント・フリーランス
豊富な経験とスキルを活かし、ITコンサルタントやフリーランスとして独立する道もあります。
企業のIT戦略立案やシステム導入支援など、より上流の業務に携わることができます。高い専門性と実績があれば、高収入を得ることも可能です。
年代別のキャリア戦略
20代:基礎スキルの習得とプロジェクト経験
20代は基礎固めの時期です。サーバー、ネットワーク、クラウドといった基本技術を幅広く学び、多様なプロジェクトを経験することが重要です。資格取得にも積極的に取り組み、技術の基礎を固めましょう。
30代:専門性の確立と実績構築
30代では、特定の技術領域で専門性を確立し、プロジェクトでの実績を積み上げます。リーダーとしてチームをまとめる経験や、大規模プロジェクトでの中核的な役割を担う経験が重要です。
40代以降:マネジメントか技術特化の選択
40代では、マネジメント職に進むか、技術スペシャリストとして極めるかの選択を迫られます。自分の適性と志向を踏まえ、明確な方向性を定めることが重要です。
市場価値を高めるために必要なスキル
クラウド技術(AWS、Azure、GCP)
クラウド技術は現代のインフラエンジニアに必須のスキルです。
AWS、Azure、GCPのいずれかで実務経験を積み、認定資格を取得することで市場価値が大きく向上します。
自動化・IaC(Terraform、Ansible)
インフラのコード化(Infrastructure as Code)は、効率的なシステム運用に不可欠です。
Terraform、Ansibleといったツールを使いこなせるエンジニアの需要は高まっています。
セキュリティ知識
サイバーセキュリティの重要性が増す中、セキュリティに関する知識を持つインフラエンジニアの価値は高まり続けています。
コンテナ技術(Docker、Kubernetes)
Docker、Kubernetesといったコンテナ技術は、モダンなインフラ構築に不可欠です。コンテナオーケストレーションのスキルは、市場価値を大きく高めます。
7. インフラエンジニアの企業選びでよくある質問

インフラエンジニアの企業選びに関して、多くの方が抱く疑問や不安に答えていきます。これらの質問への回答を参考に、自分に最適な企業選びの判断材料としてください。
大手企業と中小企業、どちらを選ぶべき?
それぞれにメリット・デメリットがあります。
大手企業は、教育体制が整っており、福利厚生も充実している傾向があるため、未経験者には有利です。
一方、中小企業は裁量が大きく、幅広い業務を経験できるため、成長スピードが早い可能性があります。自分のキャリアステージと志向性に応じて選択しましょう。
SIerとSES、どちらのキャリアが有利?
それぞれのメリットなどをしっかりと確認することが大切です。
SIerは要件定義から運用まで一貫して携われる案件が多く、上流工程の経験を積みやすいメリットがあります。
SESは多様なプロジェクトを経験できる一方、案件によっては下流工程のみを担当するリスクもあります。
SESを選ぶ場合は、キャリアサポート体制が充実している優良企業を選ぶことが重要です。
インフラエンジニアは「やめとけ」と言われる理由は?
「やめとけ」と言われる理由の多くは、ブラック企業で働いた経験に基づくものです。
下請け案件ばかりで技術が身につかない、長時間残業が常態化している、評価制度が不透明といった環境で働くと、確かに「やめとけ」と言いたくなります。
しかし、本記事で解説した8つのポイントを満たす優良企業を選べば、こうした問題は回避できます。
未経験からでも本当に転職できる?
未経験からでも転職は可能です。
ただし、「未経験歓迎」の企業の中には教育体制が整っていない企業も存在するため、慎重な企業選びが必要です。
入社前に基礎的な資格(CCNA、LPIC等)を取得し、学習意欲を示すことで、選考の通過率が高まります。
優良企業は本気で未経験者を育てる体制を整えているため、適切な企業を選べば、確実にスキルを積み上げていくことができます。
8. まとめ:インフラエンジニアの企業選びで失敗しないために
インフラエンジニアの企業選びでは、元請け比率、年齢構成、残業時間、教育制度、評価制度、福利厚生、キャリアパスといった8つのポイントを総合的に確認することが重要です。
公式サイト、口コミサイト、転職エージェント、面接といった複数の情報源を活用し、多角的に企業を評価しましょう。
特に未経験者は、本当に育てる体制がある企業を見極めることが成功の鍵となります。
優良企業を選ぶことで、長期的に成長し続けられるキャリアを築くことができます。